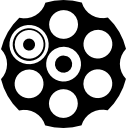はじめに
功成り名を遂げた人には、日本経済新聞の「私の履歴書」に「思い出」を語る機会があるが、私の場合はそういう事は先ずあり得ないので、記憶の薄れないうちにこれ迄のことを書き残し、たまたま興味を持ってくれた人がいれば、ウェブ上で読んで貰えるようにしようと考えた。その時には夢中だったことも、後で振り返ると寒々とした感があるが、それでも多少は波乱に満ちたビジネスキャリアだったと思う。
生い立ちと学生時代 (1939 – 1962年)
私は、兄一人、姉二人の末子として、1939年に東京で生まれた。
父は銀行員だった。先祖は北条家の家老格だったが、秀吉の小田原攻めを目前にして、殿様の子供を一人預かって田舎に身を隠し、15代にわたる家系図だけを守って、そのまま百姓として息を潜めていたらしい。15代目の当主であった祖父が米相場に失敗して一家は貧窮したが、四人兄弟の中で、父だけが辛うじて大学を出して貰えたと言う。
銀行で仕事をしている時に関東大震災にあい、周りで多くの人達が死んでいる中でも何とか生き延びた事から、「人並み以上の強運」を自認していた。50歳代の終りに胃潰瘍を患い、大きな手術をしたが、結局99歳まで生きた。生涯を通じて「人の悪口を言ったことのない人格者」と評されていた様だが、本人はそのことを喜んではいなかった。「自分は本当はもっと悪い人間だった」というのが口癖だった。
母は勝気な人だった。生家は、東京の下町、根岸、坂本界隈で青物商を営んでいたと言う。江戸城に日本で初めて外来のトマトを納めたと聞いたことがあるので、相当名の売れた商家だったのだろう。その頃の商家の娘は、未だに江戸時代の気風を残し、歌舞伎役者などにうつつを抜かしているのが普通だったらしいが、母は両親を説得して高等女学校にまで行かせて貰ったという。その為に、「変わり者」という意味で、「カワちゃん」という仇名をつけられたらしい。
私が生まれたのは東京の郊外だったが、父の転勤で、生後3ヶ月で大阪に移り住み、成人するまで主として大阪の郊外に住んだ。その間に、一時期東京に住んだこともあったが、空襲が激しくなったので、栃木県に疎開した。そのおかげで、ほんのわずかの差で東京大空襲を免れた。5歳の時に、疎開先で、大人達と一緒に玉音放送を聞いた。
高等女学校で良妻賢母教育を受けていた母は、日本が戦争に負ければ、当然子供を刺し殺し、自分も自決せねばならないのだろうと思っていたらしいが、結局何事も起こらずに、戦後の日本が始まった。
まともな食べ物はなく、常に腹をすかしていた。米国の援助物資だった家畜の飼料で作ったパンと、ふかしたジャガイモ、サツマイモが昼食の定番だった。風呂などというものはなく、母が湯に浸した手拭いで身体を拭いてくれるのが最大の楽しみだった。蚤に食われたあとが方々で膿んで酷い状態だったが、包帯とか絆創膏などというものはないので、古い浴衣を切り刻んだもので代用していた。今の時代から見れば「極貧以下の生活」だったと思う。
「シンチュウグン(米兵)に『チョコレート・ギブミー』というと何か呉れるぞ」と聞いていたので、一所懸命そう叫んでみたが、私自身は結局何も貰えなかった。しかし、時折、闇ルートで米軍の食料が入手できた。たまたまありついた缶詰のランチョンミート(現在のSPAM)が、「こんなにもおいしいものが世の中にあったのか」と思うほどにおいしかったのを今でも覚えている。
終戦後、一家は大阪に戻り、私は大阪府立北野高校から京都大学法学部へ進学した。
高校時代は結構秀才で、特に理数系に強かったので、理学部に進むことに興味があったが、実験や観察は苦手だったので、周囲が奨めた「就職に有利な工学部」には行く気がなかった。結局は、あまり迷うこともなく、「普通の就職」が可能な法学部に行くことに決めた。先生は東大受験を奨めたが、その気は全くなかった。当時から反骨精神があり、「官」より「在野」の方がよいと、何となく思っていた。
大学に入ってからは全く勉強せず、当時は珍しかったジーンズに革ジャン姿で時折自転車で学校に行くと、門衛に「部外者の学内通り抜けはお断り」と言われて、入れてもらえないこともあった。アルバイトで白タクやバーテンをやって小遣い銭を稼ぎ、漫然と遊んでいた。喧嘩が強くなりたくて、町道場に通って空手(剛柔流)を習ったが、その後大学の空手部(糸東流)に転じて副将を務めた。
当時は安保闘争が盛り上がっていたので、付き合いでデモなどに参加したこともあったが、あまり共感はもてなかった。それでも、当時の大方の若者達の例に漏れず、私も「資本主義には将来はない」とは思っていたので、選挙で自民党に投票する事などは考えてみたこともなかった。
法学部の勉強は全くしなかったが、文学や哲学の本は結構読んだ。特にアルベール・カミュやジャン・ポール・サルトル、フランツ・カフカ、オルテガ・イ・ガゼット等の著作を愛読した。日本の作家では芥川龍之介に傾倒し、若い時から晩年に至るまでの小品や書簡に至るまでを、余すところなく精読した。
伊藤忠商事に就職 (1962 – 1968年)
大学を出たら就職するのが当たり前と思っていたし、当時は新卒側の売り手市場だったから、気楽な気持で友人達と一緒に会社回りをした。たまたま友人の先輩の勤めていた三井物産の屑鉄部に行った時に、その活気に満ちた雰囲気が気に入って、父に相談したら、「商社は賛成だが、伊藤忠か住商にしろ」と言われたので、結局伊藤忠(大阪本社)に入社することになった。
父は住友銀行に勤めていたが、松下幸之助さんがオランダのフィリップス社と合弁で松下電子工業を創った時に、財務担当の副社長に招かれて、後に社長になった。中学生の時に松下さんが家にこられたことがあり、その時に頭をなでてもらったのを今でも憶えている。天才的な経営者としての松下さんの逸話は、父からよく聞かせて貰った。生々しい話だったので印象が強く、「成る程」と思うことが多かった。
伊藤忠では、機械部門に入りたいと希望を出したら、「輸出繊維機械課」に配属された。インド、パキスタン、フィリピン、インドネシアなどに、賠償や円クレジットで豊田自動織機が作る紡績機械などを輸出する課で、1年目は経理の担当、2年目からはインドの担当になった。
一年間の経理担当は、後で考えると大変大きな勉強になった。毎月の決算で課長が数字のチェックに苦労しているのを見て、それまでの大福帳的なやり方を一新して、契約毎の採算管理が出来るような新しい帳票システムを考案した。
当時ポンドの切り下げがあり、ポンド建てでやっていたロシア向けの延払取引で厖大な損が発生したので、「もし今後ドルでそういうことが起こったらどうなるのか」と思うと心配になり、自分で工夫してエクセルのような表を作り、手作業でシミュレーションが出来る方法を考案した。当時はコンピューター等というものは影も形もなく、日常の仕事はソロバンか手回し計算機だったが、もしその時にコンピューターがあれば、そのままその世界にのめり込んでいたかもしれない。
隣の「輸入繊維機械課」は、ドイツやスイス、イタリアなどから機械を輸入する「スマートで格好のいい課」だったが、羨ましいとは思わなかった。当時は「輸出で外貨を稼がなければ日本は立ち行かない」という切羽詰った使命感があったので、泥臭い発展途上国向けの仕事に誇りを持っていた。先輩達の働き振りには目を見張ることが多く、「商売の駆け引き」といったことについても多くを学んだ。
入社3年目に、かつては「相場の神様」と謳われた小菅宇一郎会長が相談役に退いたのを機に、相談役付きの秘書になった。小菅さんは情に厚い人格者で、多くの薫陶を受けたが、秘書室の仕事は全く性に合わなかったので、「営業の最前線に帰りたい」と再三陳情した結果、2年半あまりで解放された。
尤も、秘書室で学んだことも多かった。大会社のトップ人事の決まり方とか、それを巡っての色々な人間模様が、手に取るように見えたからだ。人によって差はあるが、権力に擦り寄り、主流から外れないようにそれぞれに必死に工夫している様は、あまり美しいものには見えなかった。その為、私には、「大会社で高い地位につきたい」という願望を持つことが、生涯を通じて遂に一度もなかった。「他人に真似が出来ないぐらい働き、自分で納得の出来る実績を挙げる」ということだけが、常に私の心の拠り所となった。
韓国で繊維機械の売込みに奔走(1968 - 1974年)
久しぶりに「輸出繊維機械課」に帰ると、主力市場はインド、パキスタンから韓国、台湾に変わっていた。
28歳の冬に韓国の駐在員になり2年間ソウルに住んだ。先輩はみんな外人居住区のアパートに住んでいたが、一番若い駐在員だったので割当がなく、街中で下宿した。風呂はなく、洗面も外だった。トイレは水洗式だったが、水が出ることはなく、自分でバケツで水を流さなければならなかった。オンドル式の部屋は、横になると暖かいが、座っていると寒い。市販の石油ストーブは事故が多いというので恐れをなし、結局、一冬の間、部屋の中でも厚手のコートを着たままで過ごした。
しかし、この経験のおかげで、ソウルの普通の市民の人情に触れることが出来た。若い多感な時だったので、短い駐在期間だったにもかかわらず、韓国を第二の故郷と思うまでになった。その頃に習い覚えた片言の韓国語を、今でも極力使って忘れないようにしているし、古代から現代に至るまでの韓国の歴史も、時折熱心に勉強している。
ソウル時代はよく働いた。中小企業銀行枠の輸入ライセンスというものが発給されたので、このリストをいち早く入手し、煙突に書かれたハングル文字とリストの会社名をつき合わせながら田舎回りをした。こうして一足先に見込み客との関係を作ったので、メーカーの信頼を得ることが出来、結果として、この関係のビジネスでは、当時韓国に支店を持っていた十社以上の商社の中で、1社だけで80%近いシェアを取ることが出来た。
仕事は8割方日本語で出来たが、当時は日本人に対する反感も相当大きかったから、言葉遣いにはいつも気を使っていた。4人の課員と代理店の人達との人間関係にも気を使った。商社の仕事は、大型の金融取引を除けば所詮は「仲介」の仕事だったから、韓国のお客にも日本から来るメーカーの人にも気を使わなければならない。当時は宴会では酒を無理強いすることも多かったから、来韓した日本メーカーの偉い人が酒が駄目だと、自分でその人の分まで飲まねばならず、二日酔い、三日酔いはざらだった。
韓国から帰ってしばらくは東南アジアの仕事も担当した。この間に、インドネシアには2ヶ月ほど滞在した。
32歳で結婚、同時に東京に転勤となった。東京で仰せつかったのは、機械部門全般(自動車、船舶、航空機、エレクトロニクスを含む)を統括する副社長付というポジションで、またもや秘書的な仕事が多く、あまり気が進まなかったが、その頃は日本も「もう輸出にはあまり力をいれず、輸入を増やせ」という時代に変わっていたので、「2年間この仕事をやったらその後は欧米に駐在させて貰う」という条件を認めて貰った上で、おとなしく命令に服した。
その頃の伊藤忠は、後に臨調で活躍する元陸軍参謀の瀬島龍三副社長が、「分権組織の総合商社にも全社を横断する参謀本部的な組織があるべきだ」という考えを強く打ち出し、世に言う「瀬島機関」というものが脚光を浴びていた時代だったが、私が仕えた機械部門担当の野村福之助副社長は、スマートで瀬島さんに負けず劣らずの頭脳明晰な人ながらも、繊維部門の現場でたたき上げた人だったので、瀬島さんとはかなりの意見の相違があった。
山崎豊子の「不毛地帯」に描かれているような対立関係とは全く性格の異なったものではあったが、少しはそれに似た出来事もないではなかったので、総合商社特有の大型プロジェクトにまつわる機密事項の取扱いと相俟って、未だ若輩だった私の日常の仕事にも、若干の緊張感があったのは事実だ。
ニューヨーク駐在時に通信機ビジネスを開拓 (1974 - 1982年)
2年間の東京勤務が終わると、約束通り、たまたま空いたポジションがあった「シカゴ駐在員」にして貰った。しかし、「食品、医療、包装などの分野で米国から輸入出来る新しい機械類を、何でもよいから探せ」というこのポジションは、既に時代遅れだったし、独立採算で運営するには無理があり、1年でニューヨークに転勤になった。
ニューヨークでも採算に乗るビジネスはなかなか見つからなかった。自分で稼げないと、セクレタリーさえ満足に使わせてもらえない。
ユダヤ系の米国企業が作るダンボール製造機器を、アルジェリア向けに石川島播磨が売り込んでいた製紙プラントの中にもぐりこませるとか、皇帝が強大な力を持っていた当時のイランが、イラクと束の間の関係改善を計った時に、イランの港に滞在するイラクの税官吏宿舎用にアメリカ製のモバイルホーム(家具調度品付きの簡易ホーム)を輸出するとか、当時脚光を浴びつつあった「国交回復前の米中貿易」の仲立ちをするとか、色々なことを試みたが、何をやってみても、そう簡単には結果は出ない。
「どうして食い扶持を稼いだものか」と思いあぐねていたところ、たまたま以前に一緒に仕事をした先輩が東京本社の「通信プラント部」の課長をしているのに気がついて、この人に「貴部だけがアメリカと全く関係を持っていません。私に年間1万ドル払ってくれたら何でもやりますから、考えてみてくれませんか」という手紙を書いた。この人は最後まで1万ドルは払ってくれなかったが、その代わり日本製の電話機などのカタログの束を送ってきた。
見るからにダサいカタログの束を見て、「こんなものがアメリカで売れるわけはないじゃあないか」と腹を立て、まとめてゴミ箱に放り込もうとした時に、ちょっと変わった形の電話機の写真と英文でタイプされた二枚の紙が目に留まった。これが、松下通信工業(現在のパナソニック・モバイルコミュニケーション)が世界に先駆けて開発したマイクロプロセッサー制御のボタン電話システムだった。松下はこれを電電公社にもっていったが全く相手にされず、「それでは輸出するしかない」ということで、藁にもすがる思いで各商社に持ち込んでいたらしかった。
それから色々な苦労があったが、結局、ここから始まった「ビジネス用電話システム」の対米輸出が、結構大規模なビジネスになる見込みがついたので、本社の「通信プラント部」の中に課を一つ新設してもらって、そこの課長として帰国することが出来た。私が39歳の時のことで、それ以来、私の「通信」との35年近くに及ぶ関係が始まる。
しかし、それからの約5年間は苦労の連続だった。順調に拡大していた松下のビジネスも、大型PABXシステムを手掛けだしてから技術の壁に阻まれ、トラブルが続発した。課員にまともに英語の出来る人間がいなかった為、課長の私自身が夕刻の5時頃から横浜の松下の工場に出向き、技術者の作るトラブル対策の手順などを翻訳して米国の販売業者に送り、最後の一人になるまで仕事をして深夜に帰宅するような生活を続けた。
現地に飛べば飛んだで、客先のセクレタリーに頼み込んで、「電話が途中で切れる。こんなことでは仕事にならん」と怒り狂う個々のユーザーからログを取ってもらったり、終業後のオフィスで深夜まで回線の繋ぎ変えをしたりと、泣きたくなる様な仕事ばかりが多かった。にもかかわらず、松下側からすれば、「そろそろ伊藤忠に手数料を払い続けるのは止めたい」と思うのは当然で、色々な局面で仕事から外される危機があり、私は「仲介業者」の悲哀を噛み締めさせられた。
課長として課員を路頭に迷わせるわけには行かなかったから、私は多くの屈辱に耐えたが、自分自身の心の中では、「仲介業なんかは早くやめて、メーカーで仕事をしたい」という欲求が抑え難くなっていた。長い間ずっと松下通信工業の技術開発チームの中で一緒に仕事をしていたので、門前の小僧も経を読み、特に新しい機種を創り出す事に対する興味が、人一倍強くなっていた。
この為に、後に某メーカーから責任のあるポジションを提示されて誘われた時には、真剣に転職を考えた事もある。
「ベンチャービジネス」への興味 (1982年 - 1986年)
しかし、その頃、隣の「情報機器部」では、産業用のドットプリンターをビジネス用のプリンターに使うアイデアを自ら商品化し、当時急成長していたアップル社などにOEMで納める仕事が大成功を収めつつあり、破竹の勢いだった。つまり、隣の部は、それまでの「仲介業者」としての商社の枠組みから、既に脱却しつつあったのだ。
これを横目で見ていたので、自分も「通信」の世界で何とかそのような路線を歩みたいと考えた。色々と思いあぐねたが、NTTへの依存体質が強い日本の通信機メーカーの壁は厚い。結局、「米国やイスラエルのベンチャー企業と組み、彼等が開発したシステムを日本の家電メーカーに作って貰って、世界中で売るしかない」という結論に達した。(ベンチャービジネスは、米国ではこの頃から脚光を浴びつつあったが、当時の日本にはまだその萌芽は見られなかった。)
勿論、その間にも、一刻も休む暇なく、実に色々なことを手掛けた。韓国が初めて自動車電話(現在の携帯電話)サービスを始めると聞きつけると、単身アメリカの中西部に飛んで、当時モトローラと並んで唯一AMPS方式の自動車電話システムを開発・製造していたE. F. Jhonson社を口説き、その足で、今度は韓国に飛んで、韓国の電電四社の一つであった東洋精密(OPC)に、何の紹介もなしに飛び込んだ。三星(サムスン)はNECと、金星(現在のLG)はモトローラと既に提携していたので、選択肢は限られていたのだ。
その後色々な経緯があったが、両社の間に立って一人で走り回り、最終的に、E. F. Johnson社の技術をOPC社にライセンスするプロジェクトを何とか纏め上げることが出来た。これが私と「携帯電話」との初めての出会いだった。(このビジネスでは、うまくいけばロイヤリティーの一部が末長く伊藤忠に入る目論見だったが、両社共その後業績不振に陥り、残念ながらこの努力は結局報われることはなかった。)
あれやこれやしているうちに、再びニューヨーク駐在を拝命した。今度は堂々たる「伊藤忠アメリカ会社 上級副社長兼エレクトロニクス部長」の肩書きだったが、カリフォルニアに最盛期で四百人程度を抱える独立法人を持っていた「情報機器部門」とは全く関係なく、「通信」と「民生電子機器」の分野で、一人で一から仕事を創らなければならない立場だった。(早くからアメリカで仕事をしていた家電部門は、既に米国展開に失敗して撤退した後だった。)
会社がこの時期に私をニューヨークに送り込んだ理由の一つには、「AT&Tが分割された」事もあった。分割によって生まれた七つの地域電話会社(RBOCS)は、それぞれに新しい仕事を手掛ける意欲を持っており、時あたかも「コンピューター技術を取り入れたビジネス用電話システム」がブームを迎える気配だったことから、自分でも、「ベンチャーと組めば、この分野で何か大きな仕事が創り出せるかもしれない」という期待を持っていた。
しかし、結論から言うなら、「電話システム」と「ベンチャー」は相性が悪かった。情報機器の売り込み先は各企業の情報システム部門であり、この部門の技術者には新しいものに興味を持つ人達が多かったが、電話システムの売り込み先は総務部門であり、彼等は新しい物を下手に取り入れて失敗することを恐れていた。RBOCS七社も、実際に仕事をするとなると動きが遅く、上層部は興味を示してくれても、実務部隊は思うように動いてはくれなかった。
あれやこれやで、3年に及ぶ悪戦苦闘にもかかわらず、投資したベンチャーの殆どは壊滅した。それだけならよかったが、ベンチャー投資に飽き足らず、自らベンチャービジネスとして立ち上げた社員数15人程の100%出資会社(CICS社)も、存亡の危機に瀕していた。
「ベンチャービジネス」の挫折 (1986年 - 1988年)
この会社は、私が自分自身で長年構想を暖めていた多機能電話システムを、日本のシャープや大興電機等に作ってもらって、それを米国で販売する為の会社だった。私が開発した商品は、当時七つの地域電話会社(RBOCS)がAT&Tに対抗する戦略商品として売り込もうといていた「セントレックス」のサブシステムとなる筈のものだったから、これなら、彼等の販売組織にも興味を持ってもらえる筈だと踏んでいたのだったが、結果は思うに任せなかった。
「人に頼っていては駄目だ。自分自身で世の中のニーズを先取りして、既存の要素技術を結びつけ、独自の商品を創り出す必要がある。」その様に一人秘かに思い詰めていた私は、「Be creative or die(創造しないのなら、死んだ方がまし)」という標語(米国の独立戦争時代の標語「Be free or die」をもじったもの)を自分で作って、額に入れてCICSの社長室に掲げた。この仕事を始めた当初は、このように気持ちが高揚していたのだが…。
第一号商品として企画した最新鋭の高機能電話機(愛称ESCOM)は、エグゼクティブ同士、或いは秘書とエグゼクティブとの連携機能に重点をおいた「システム志向」の商品だったが、単体としても、これまでにない最高級機と認められることを目標とした。大型のLCDディスプレイと必要な時に引き出せるQWERTYキーボードを具備し、「電話帳」や「ワンタッチコールバック機能」は勿論、「システム内でのメッセージ交換」、「スケジュール管理」、「特定のデータサーベースから必要情報を取り出せる機能」などを内蔵していた。一九八六年の時点だから、世の中に全く存在していなかった機能も多かった。(例えば「グループ内でのメッセージ交換機能」はE-Mailと名付けたが、この呼び名を使ったのは世界で初めてだったと思う。)
このシステムの先進性には業界の中でも注目してくれる人が多く、或るコンサルタントの推薦で国防省の高官のオフィスに早々と一システム納入できたし、Dow Jones社は自社の株価表示システムと連動させてくれて、「Dow Phone」というパンフレットまで作ってくれた。しかし、如何せん、このシステムは、売り出してからすぐに致命的な欠陥を露呈した。
私の未熟さ故に、普通の多機能電話機を作る感覚で「機能決め打ち」でソフトを作り込んでしまったのが最大の失策だった。この為、「客からの変更要求に全く応えられない」という問題が早々と露呈した。「売込みにも販売後のトレーニングに手間がかかり過ぎる」「電話システムの拡張性が限られていて、大口の見込み客の要求に応えられない」等々の問題も生じ、あてにしていたRBOCSの販売部門は、「これらの問題が解決するまでは販売には踏み切れない」として「様子見」を決め込み、動いてくれなかった。
そうこうしているうちに、一向に売れない初期ロットは、たちまちのうちに在庫の山になった。折からの急激な円高にも打たれた。(尤も、私は「円高があろうとあるまいと、売れないものは売れなかった筈」と考えていたので、円高を言い訳にする事は一切しなかった。)
その頃の私には、別途、「伊藤忠アメリカのエレクトロニクス部長」としての広範な職責もあった(その中には、「NTTと一緒にジャマイカでテレマーケティングの会社を創る」という面白いプロジェクトもあった)ので、CICSの社長には早い時期に然るべき米国人を雇う予定だったのだが、こういう状態では誰もこんな会社には来てくれない。仕方がないので自分自身で社長兼務を続行して、毎日の半分以上の時間をこの会社の為に使わざるを得ないという破目になった。
しかし、朝早くから深夜に至るまで働いても、人間が一日に使える時間には限界がある。本社から頼まれる仕事は、「どうしても」という案件以外はついつい他人任せになる。本社から見ると、「あいつは勝手な事ばかりしていて、全く頼りにならない」という事になってしまうのもやむを得なかった。
こうなれば、いくら何でも東京本社での信用は完全に失墜する。先ず「CICSにはこれ以上金は出せない」という限度額を突きつけられた。ということは、「残り少ない時間内に目覚しい業績の好転がない限りは、CICSは倒産するしかない」事を意味する。
「これまでに使ったのと同じぐらいの金を更につぎ込んで、もう1年かけてESCOMを一から作り直し、その間に、別途開発が終わっていた『一般用の安価な電話システム』の方を先行販売することにすれば、RBOCSの販売組織を動かすことは十分可能だ」と考えていた私は、最早何を言っても聞いて貰えそうにない東京本社に頼ることを断念し、これまでに付き合ってきていたベンチャーキャピタリストを口説こうと考えた。
しかし、会社の名前をIBMの向こうを張ってICM(International Communication Machine)とした程の野心的なビジョンや、何日も徹夜して作った詳細な事業計画は、それなりにかなり評価されたが、「それでは何故伊藤忠はこの可能性を放棄しようとしているのか」という問いにはうまく答えられない。そのうちに資金切れの期日はどんどん迫ってくる。情況を察しはじめた従業員達の空気も不穏になる。「倒産寸前の会社」というものはどこでもそういうものなのだろうが、毎日が地獄のようになった。
エレクトロニクス部長を解任された上、「小さなオフィスを一つ用意しますから、当面は既に売ってしまった商品のアフターサービスだけを、一人でやっていてください」と、本社のかつての自分の部下に求められたこの時期が、私にとっては文字通り「人生のドン底」だった。「成程、自分一人なら夜逃げも出来ようが、伊藤忠の名前で売ってしまった商品ならアフターサービスをしないわけにはいかない。会社がお前一人でやれというのなら逃げられないというわけか!」そう考えると、流石に目の前が真っ暗になった。
しかし、誰を恨むわけにも行かない。全て自分で決めて自分でやったことだ。この頃になると、このような事態を招くに至った自分の多くの「判断の誤り」が、自分自身でもよく分かるようになっていたので、拭っても、拭っても、頭から離れない悔悟の念に、身を切られるような毎日が続いた。(この辺の話は、後述する久慈毅著「新規事業室長を命ず」で少しだけ触れられている。)
それからの必死の努力のおかげで、辛うじて「従業員の全員引き取り」と「アフターサービス」を西海岸にあった或る新興企業に引き受けて貰えたので、私自身は虎口を脱することが出来たが、その後この会社がこの商品ラインを生かして成長したという話は聞いたことがなかったから、結局は大きな迷惑をかけたのだろう。その事を思うと、今でもとても辛い。
会社売却の交渉を通じて、相手方に対して真実を糊塗した事は一切ないと断言出来るが、「夢を語り過ぎなかったか?」「気掛かりな事を全て洩れなく話したか?」と問われれば、胸は張れない。如何に「自分が生き残る為」だったとは言え、この事については、今に至るも、私の心の中で罪の意識が消える事はない。
屈辱に耐えての帰国 (1988年)
その後、本社からは「すぐに日本に帰って来い」という指示があったが、その気にはなれず、一人で秘かに米国での新しい職場探しを始めた。「あんたは日本に帰れば仕事があるのだからいいよな」と嫌味を言ってきたCICSの米国人の部下達に、「何を言うか。勿論私も伊藤忠を辞める」と大見得を切っていた手前もあり、自分だけのこのこ日本に帰るわけには行かないと思っていた。
つまらない「男のプライド」から、「伊藤忠時代より地位や給料が下がるのは嫌だ」という気持が先行し、この為に仕事探しは難航したが、そのうちに、これまでの仕事を評価してくれていた或る米国人の斡旋で、ノースキャロライナにあるノーザンテレコム社の交換機事業部のVPに採用して貰うことがやっと決まった。
正式な採用通知を貰った時には心底からホッとしたが、ホッとして伊藤忠に辞表を提出したその直後に、国際事業を巡っての同社の複雑な内部事情(カナダ本社と事業部との綱引き)が判明、同社に入っても難しい立場に立たされる心配が出てきた。自分の本領は何といっても「日本をよく知っている」という事だ。それなのに、内部抗争に巻き込まれ、その得意分野を生かせられなければ、よい成果は出せるわけがない。米国の会社だから、成果が出せなければやがて放り出される。私は頭を抱えた。
「この状況下で自分はどうすればよいのか?」しばらくの間、この事について相当思い悩んだ。ノーザンテレコム以外でもあらゆる可能性をチェックしたが、そんなに簡単にいい話は見つからない。一旦無職になって、また一から職探しをするとなると、家族の生活を守っていける自信が持てない。
そうなると、やはり、一旦は米国での全ての可能性を諦め、日本に帰るのが一番良いのではないかという結論になった。そこで、遂に意を決して、恥を偲んで伊藤忠の本社に電話をした。「あのう、辞表を出してしまっているのですが、もしかして、今からでも撤回させてもらうことは出来るのでしょうか」と恐る恐る聞くと、「ああ、いいよ。やってもらいたい仕事は山ほどあるから、帰ってきなさいよ」という返事が返ってきた。
思えば思う程に、堪え難い程の屈辱的な思いがこみ上げてきたが、家族の事を考えるとやむを得なかった。何よりも3人の子供達の教育を犠牲にするわけにはいかないと思った。こうして、私は、書類を整えて伊藤忠への復帰を認めて貰い、帰国の日取りも決まった。
しかし、どんな会社のどんな組織でもそうだろうが、「相当額の損失(今から考えると、さして大きな額ではなかったが)を出した上に、既に辞表を受理して退社が決まっている社員には、最低の評価点をつけて、他の社員への得点の配分を少しでも良くする」のが組織の管理者の常識だ。復帰が決まった時には、既にこの評価は人事部に登録済みだったので、採点者としても今更書き換えるわけには行かない。こうして、私の東京本社への帰任は、CCCという史上稀な「最低評価」の烙印を背負っての帰任となった。伊藤忠の内規では、こういう評価が一旦付いてしまうと3年間は消えない。
「通信事業部長」の仕事 (1989 - 1994年)
しかし、ちょうどその頃の伊藤忠は、これまでの商社の枠を破って「自ら通信事業を営む」方向へと大きく舵を切っていたところだったから、人材が払底していたのだろう。「最低評価」を背負っての帰任だったにもかかわらず、帰国の翌年には、「国際通信事業室長」として、トヨタ自動車や英国のケーブル・アンド・ワイヤレスとの合弁であるIDC社の運営の本社側の責任者となり、その翌年には、伊藤忠の看板事業であった衛星通信事業などを統括する「通信事業部長」となった。
その間に、部下の一人が熱心に進めていた「NTTドコモの携帯端末の販売店の展開」にも関与した。ちょうど「携帯電話機の売切り制」が始まったところで、業界の盟主たるドコモといえども、まだ全てが手探り状態だったので、商社からのアプローチにはそれなりの魅力があったのだろう。この仕事では私自身の貢献は殆どなかったが、「携帯端末の販売事業」は伊藤忠が他商社に先駆けたものであり、その後長年にわたって、この仕事は部門の最大の稼ぎ頭となった。
この件だけに限らず、この頃の商社は全てに貪欲で、世間も商社に期待していたから、多種多様な案件が国の内外から頻繁に持ち込まれ、その評価に毎日が目の回るような忙しさだった。少なくとも、一年に二つか三つの新規事業にGOサインを出したが、10件近くは却下した。米国駐在中に散々苦労した甲斐があって、「事業性の確認」には極めて厳しく対処するようになっており、例えば、イリジウムのような低軌道衛星事業等については、各社が次々に参入するのを横目に、「事業性がない」と確信して不参加の方針を貫いた。
しかし、私自身は、決して大企業的なバランス感覚に回帰したわけではなかった。CSKの大川功さんから声をかけてもらった「パンナムサット(コムサットに対抗する純民間企業)」は、「必ず成功する」と踏んで、本気で資本参加の可能性を追求した。しかし、この頃になると、さすがの伊藤忠も「衛星関連事業にこれ以上突っ込むのは危険」と判断するに至っていたので、力不足で上層部を説得出来なかった私は、結局この件を途中で断念せざるを得なかった。
もしこれをやっていれば、当時の伊藤忠全社の丸一年間の経常利益に相当するようなキャピタルゲインが得られていた筈だったので、この事だけは今考えても残念だ。それ以上に、本能的にこの仕事の可能性を嗅ぎ取り、最後まで執念を燃やしていた大川さんの期待を裏切ってしまったのは心苦しかった。
小さな仕事も色々手がけた。これも途中で投げ出してしまったが、日本初の「通信回線を使った野球ゲーム(実際のデータと連動したチームを率いて『監督の腕』を競い合うゲーム)」の開発では、業界誌から賞をもらったこともある。
これは私とは関係のないところで決まったことだったが、その頃、伊藤忠は、東芝と共に、米国のタイムワーナーに5億ドルの大型投資を行い、この流れで、日本でのケーブルTV事業の立ち上げも共同で行っていた。(この関係で、私は一時期タイムワーナーのExecutive Boardのメンバーだったこともある。)ケーブルTV事業はタイムワーナー社の目玉事業だったから、私もそれなりに全力を上げて取り組んだが、一方で、日本でのケーブルTV事業の推進は、後述する直接衛星放送事業とかぶるところもあったので、その扱いにはそれなりの苦労があった。
また、ケーブルTV事業の真の価値は、後に言われる「トリプルプレイ」にあると、その頃から私自身は確信していたので、少し方向性の違う「フルサービス・ネットワーク」というものに注力していたタイムワーナー社とは、戦略的な考え方が異なっていた。また、これは結局は杞憂に終わったのだが、「NTTが将来多くの家庭の電話線を光ケーブルに張り替えたら、ケーブルTV会社はとても対抗出来ない」と考えていた私は、どうしてもケーブルTV事業にのめり込む気持ちにはなれなかったのも事実だった。
だから、表面的には友好的に仕事を進めながらも、「こういった考え方の違いが、将来何か大きな問題を引き起こすのではないか」という不安が、私の心の中には常に付きまとっていた。そして、現実に、この事は私が考えていた以上に大きな問題を私にもたらしたようだった。「基本的な考え方の違い」はどうしても日常の言動に出る。タイムワーナーの側としては、実は私以上にこの不安を感じていた様で、「このプロジェクトの責任者を松本から誰か他の人間に変えて欲しい」と、密かに伊藤忠の上層部の方に働きかけていた事を、私は後で知った。やむを得ない事だった。
通信衛星会社の合併と衛星放送会社の設立 (1994 - 1995年)
この様に、この時代には、私の周辺では実に色々な事が同時並行的に起こっていたが、この時代に私が成し遂げた最大の仕事は何だったかと言えば、やはり「通信衛星会社の合併による四商社の大同団結」と、それに連動した「直接衛星放送会社(現在のスカパー)の設立」だったと思う。これだけは、「自分がその時期に伊藤忠にいなかったら、恐らく実現出来なかったのではないか」と、今でも密かに自負している。
当時、伊藤忠は、三井物産と米国のヒューズ社との合弁による通信衛星会社JSATの筆頭株主であり、JSATは三菱商事系の会社と日夜激しく競合していたが、ここに日商岩井(現在の双日)と住商が、第三の衛星会社SAJACを設立して参入しようとしていることが分かった。実際に仕事をしていれば、衛星通信にはそんなに使い道があるわけではなく、市場は既に飽和状態にあるのが分かるのだが、「他人の花は赤い」らしく、日商岩井や住商は、私から見ると「非現実的な夢」を持っているように思えた。
これを分かってもらう為には門外不出の市場情報を出すしかないのだが、まさかそれは出来ない。この為に、先ずは、日商岩井に対して楽観的な調査報告を出していた三和銀行系の調査会社を説得することからはじめる必要があった。話を分かりやすくするために、私は「業界全体の損益計算書」まで作った。
当時の伊藤忠の米倉社長は、衛星会社の合併方針は承諾してくれたが、「伊藤忠が頭一つ上に出ること」だけは絶対条件として譲らない。その為には、20%以上の株式保有に拘る米国のヒューズ社にどうしても退出してもらう必要があり、これは極めて困難な交渉となった。米国の会社は交渉がしたたかだが、彼等の条件を飲んでしまえば日商岩井や住商が収まらない。
しかし、合弁契約書をしらみつぶしに読んでいると意外な穴が見つかったので、これを盾に、普通の日本人はやらないような厳しい交渉をして、何とか目的を果たした。こんな交渉のやり方は、「目的の達成」よりも「友好関係」を重視する上司に相談すれば止められることは分かりきっていたから、全ては私の独断でやった。水面下でこの様な苦労があった事は、殆ど知る人もないだろう。
衛星会社の合併交渉と並行して進めたのが、四商社合弁の直接衛星放送会社(現在のスカパー)の設立だった。
その頃の伊藤忠は、音楽とスポーツの分野で、アナログ方式の通信衛星を利用する二社の番組供給会社に投資していたが、視聴者が少なく、毎月一億円以上の赤字を垂れ流していた。これを何とかしなければならない。NHKが視聴料をとっている上に、地上波放送が充実している日本では、余程のパラダイムシフトがない限り「有料多チャンネル」の魅力は訴えられないと私は考え、このパラダイムシフトを自ら創り出すしかないと決意した。
具体的に考えたことは、50から100チャンネルの規模のデジタル方式のプラットフォームを新たに創り出すことだった。今でこそ、「プラットフォーム」という言葉が普通に使われているし、「受託放送会社」というものも制度として定着しているが、当時としては極めて斬新な発想だった。
共通のプラットフォームの上に、各社が既にやっている番組供給会社を乗せ、更に幅広く新規参入者を求めた上で徹底的な宣伝をすれば、既存各社を黒字転換させると共に、システム全体を採算に乗せることも出来ると私は考えた。番組供給事業ではケーブルTV事業に注力していた住商がかなり先行していたから、衛星会社の合併がなければこの様な構想はもともと成立し得なかっただろうが、幸いにして4商社の大同団結が曲がりなりにも成立していた為に、この構想を一気に実現させることが出来た。
アメリカには、同様の構想を持った会社として、既にヒューズ社が経営するDirecTV(後に三菱商事と提携して日本に進出)が存在していたが、ライセンス料が高いので魅力は感じられず、「先手を取れば独自方式で勝てる」と踏んだ。(米国の技術に頼らずとも、ソニーなどには十分その力があると考えていた。)早い時点で、私一人で一気に企画書を書き上げて、郵政省(当時)や業界の有力者の支援を取り付け、それから他の三商社に話を持ち込んで、数ヵ月後に企画会社の設立に漕ぎつけた。この辺の事情を知っている人はもう今は殆どいないだろう。
結局避けられなかった伊藤忠との離別 (1996年)
しかし、この間に、タイムワーナーとの関係を始めとして、周辺では色々なことが起こり、衛星事業に関係しての4商社間での綱引きも始まっていたので、様々な思惑が交錯する社内外の駆け引きに、私は嫌気がさすことが多くなっていた。
その頃には、私は通信事業部長から新設のマルチメディア事業部長に横滑りし、その後、「情報産業」「通信・メディア」「航空機・防衛産業」を統括する「宇宙情報部門」の部門長代行に就任していたが、この部門の部門長(取締役)には、結局入社年次で一年後輩になる「稼ぎ頭の情報産業本部」の出身者が選ばれた。当然といえば当然の事だったが、こういう流れになると、これ以上伊藤忠にいても昇進のチャンスはあまりないのも事実だ。
いや、仮に昇進のチャンスがあったとしても、そこで自分の思う方向に会社を持っていけるという自信は、私には全くなかった。少なくとも情報通信産業の分野では、主力は全て「総合商社」の枠の外に出てそれぞれの道を歩み、本体は最小限の人員で「投資」のみを行うべきだと私は考えていたが、その様な過激な考えが上層部に容れられる可能性は、当時は殆どなかった。
後に急逝する私の当時の直接の上司の森亮人さんは、次期社長が確実視されていた人で、私は彼から「政治的な動き方」等については実に多くのことを学んだが、経営についての考え方は相当違っていた。
(ちなみに、私の退社後、急逝した森さんに代わる社長候補に急浮上した丹羽宇一郎さんの方が、「経営理念においては自分と近い」と私は思っていた。丹羽さんは私と同期入社で、私とは仲もよかった。既に退職していた私を、彼は或る日夕食に招いてくれて、「ここまで来たら、自分が腹を決めて社長になり、積年の膿を全て出す」という決意を、わざわざ披露してくれた程だった。丹羽さんはその後伊藤忠の経営を軌道に乗せて「大物財界人」として名を売り、後に中国大使になった。)
何れにせよ、この様な状況下では、結論は目に見えていた。私は、常日頃から、後輩の配慮で関係会社の役員に「天下る」様なことだけは絶対にしたくないと思っていたので、「そろそろ伊藤忠を辞める汐時かな」と考えるに至ったのも当然だった。思えば、48歳で失意に打ち拉がれて米国から帰国し、「伊藤忠に在籍するのはしばらくの間」と考えていた時から、知らぬ間に7年以上が経っていたのだ。
「伊藤忠から離れたいと」いう気持を持った背景には、実はNTTの問題もあった。伊藤忠の基本的な戦略は、「衛星通信や国際通信事業で世話になっていたNTTとの緊密な関係を堅持し、その力を利用して日本の情報通信産業界での地歩を固めていく」ということであり、それは伊藤忠のおかれた立場からすれば極めて理にかなったものではあったが、私の目から見れば、主体性のない「小判鮫商法」のようにも見えた。何れにせよ、「通信の自由化を梃子に新興勢力をつくり、既存勢力に対抗したい」という自分の「心情」とは、基本的に相容れないものだった。
ちょうどその頃、経団連では、各社の部長級で構成される「情報通信産業の将来像を考える」タスクフォースが、NTT分割問題についての意見具申を求められていた。私はその構成メンバーに選ばれていたので、そこでは「会社の立場」と「自分自身の信条(心情)」との相克に深く悩むことになった。「NTTの組織防衛」に組みすることは、伊藤忠の立場としては当然の義務だったから、私も実際にそうしたが、自分の一生を委ねる選択としては気が進まず、内心は鬱々としていた。
この事には別の側面もあった。副会長を最後に伊藤忠から離れた瀬島龍三さんは、伊藤忠の中でもなお隠然たる影響力を持っていたが、彼はNTTの取締役にもなっており、伊藤忠とNTTを結びつけることに熱心だった。従って、伊藤忠の中にとどまる限りは、事の如何を問わず、NTTと事を構えることなどは不可能と言ってもよいと思われた。
しかし、大袈裟に言えば、「こんなことをしていては、日本の情報通信産業は米国などに比べて大きく後れを取る」というのが、その当時からの私の強い考えであり、その後のどんな時でもその考えが変わることはなかった。NTTには親しい人が沢山いたし、そういう人達は全て素晴らしい人達ばかりだったが、「組織になると、何故か極端に閉鎖的で保守的になる」と私は思っていた。
色々なことが重なり、次第に決意が固まっていった。「そのまま伊藤忠グループの中にとどまるという選択肢は、どう考えてみてもない」と思うに至る一方で、「人生は一度しかない。もう一度ベンチャーで勝負して、自分の基本的な考えが正しかったことを証明してみたい」という高揚した気持もあった。
その頃には、日本でもベンチャービジネスというものに対する理解は高まりつつあったし、今度は初めから「通信」にこだわらず、また「ハードウェア」にもこだわらず、ネット上で動くユニークなアプリケーションの世界で勝負すれば、勝算は十分あると考えた。明確なアイデアがあったわけではないが、ビジネスマンを対象とする「ソシアル・ネットワーク」のようなものの構築を、漠然と考えていた。もし実現していたら、ずっと後になって出てくる米国のLinkedInに近いものに発展していたかもしれない。
経過措置としての「ジャパン・リンク」の設立 (1996 - 1998年)
当時は私のような立場でそういうことをする人は殆どいなかったので、世間の人達は随分驚いたようだったが、とにかく私は伊藤忠を辞めた。
「ちゃんと食っていけるだろうか」という不安は勿論断ち切れなかったが、家族には「生涯所得を倍増する」と強がりを言って、とりあえず「(株)ジャパン・リンク」というコンサルタント会社を創った。
見栄を張って資本金1,000万円の株式会社にしたが、従業員はゼロで、ニューオータニホテルの隣にセクレタリープールを使えるオフィスを借りた。ネットで見つけたアウトレットで安い中古のビジネス家具を買い、子供達に手伝ってもらって小さなオフィスに運び込んだ。取りあえずは、これまでの人脈を使ってコンサルタント業を二年間やり、この間に新しい事業を創り出す準備をしようという計画だった。
コンサルタントの顧客としては、「同じ分野ではかぶらないこと」を原則とし、固定通信では「米国のスプリントとドイツテレコム、フランステレコムの合弁会社であるグローバル・ワン」、放送関係では「CBS(米国三大ネットワークの一つ)を買収したウェスティングハウス」、移動体通信では「CDMAという新技術を開発したクアルコム」、エレクトロニクスメーカーでは「日本メーカーの中では一番動きが早そうなシャープ」、それに、伊藤忠時代の上司が社長になっていた「ファミリーマート」、伊藤忠のお情けで付きあってくれた「伊藤忠テクノサイエンス」、色々な切り口で個人的にも関係が深かった「衛星通信会社のJSAT」といったところに固定客になって貰い、後は個人的な関係を頼っての個別案件の受注だった。
某地上波放送局から、極秘で「BSデジタル放送サービスのあり方について」のアドバイスを求められ、提言書を出したこともある。(「広告放送と有料放送を組み合わせる」「有料放送部分については民放五社が連携して時間的にかぶらない番組構成にする」等のユニークな提言をしたが、結局相手にはされなかったようだ。)
「60GHzのポイント・トゥ・ポイントの無線を、東京都が下水道管の中に敷設する光ケーブルと組み合わせて、東京全域に自己増殖型の超高速通信網を構築する」という、ややドンキホーテ的な構想を色々なところに売り込んだこともある。
グローバル・ワンの仕事は押しかけのようなものだったが、私としてはかなりの思い入れがあった。その頃、スプリントと競合していたMCIが英国のBTと組んで野心的なプロジェクトを進めようとしており、日本政府もその様な動きに神経を尖らせていたので、「NTTが国際的なIP通信網でグローバル・ワンと組む」という姿が描けないかと思い、「それまでの『ベストエフォートのIP網』ではなく、『コントロールされたIP網(現在のNGNのようなもの)』の共同研究を、グローバル・ワンの側からNTTに申し入れる」ことを、密かに画策しようと思っていた。(しかし、この様な構想は、スプリント社内の一部の人には興味を持って貰えたものの、あまりに時期が早すぎたので、具体化に至るには遠く及ばなかった。)
その頃は、「通信」と「放送」と「インターネット」を一体と考える「マルチメディア」という言葉が脚光を浴びていた時だったので、この全てにほぼ均等に関与してきた自分のような存在は貴重だと自負し、当初はこの全ての分野に顧客層を広げたことに密かに誇りを感じていたが、この全てを常によく勉強をしておくことは、実際には不可能に近いことがやがて分かってきた。ウェスティングハウスのマイケル・ジョーダン会長とクアルコムのアーウィン・ジェイコブス会長の訪日時期が重なりかけて、ハラハラした事もある。
そのうちにCDMAの日本導入の可能性が高まり、クアルコムの仕事が多くなってきた上に、クアルコムの半導体部門が日本にオフィスを作る構想を固めつつあったので、思い切って当初の「ベンチャー企業設立」の構想を捨て、クアルコムに入社することに決めた。知れば知る程クアルコムの技術陣は優秀であり、彼等が開発したCDMA技術の潜在力は、想像を絶するほどに大きいものであることが分かってきたからだ。
「クアルコム・ジャパン」の設立 (1998 - 1999年)
CDMAの日本導入は、モトローラのボブ・ガルビンと京セラ(DDI)の稲盛会長が意気投合して進めてきていたものだったから、クアルコムの貢献はさして大きくはない。それでも、最後の土壇場ではかなり重要な貢献をしたと思う。途中まではコンサルタントの立場での仕事だったが、最終段階では新設のクアルコム・ジャパン株式会社の社長として関与した。
この会社の社長は、本社側では当初は典型的なアメリカ人のエクスパトリオットを考えていたが、コンサルタントの立場から「日本人にした方が良い」と主張し、その上で自分自身を推薦した。やるからには、外資系の会社によくあるような「本社の使い走り」のような仕事はしたくなかったから、それなりの格を作る為に、「トップ直結の組織にすること」を絶対条件にし、自分の給料についても、敢えて高い水準を要求した。
(因みに、ここで頑張った事は後々大いに役に立った。通常の外資系企業では、本社の各部門がそれぞれ海外店に自分の部下を持ち、彼等は本社の顔色ばかりを見てそれぞれがバラバラに動くのが普通だ。この為、各部門が連携して戦略的に動くことが出来ず、客先からも「方針が一貫しない」と苦情が出ることがある。しかし、私はトップに直結していた為、各部門の長といえども、日本人の部下を勝手気儘に顎で使うことは許さなかった。英語でのコミュニケーションが下手な為に誤解を受けて、危うくクビになりそうだった日本人社員を何度か救うことも出来た。)
クアルコムに関連して一つ私の大きな誇りとなったことは、それまで海外展開のあり方については全く無知だったクアルコムが、「海外店のトップはその国の人間にする」という原則を作り、現実に例外なくそれを実行してきたことだ。これは、日本での成功を、韓国へ、中国へ、更にインドや東南アジア諸国へと広げていったからであり、その節目々々で、私はそれなりの役割を果たしたと自負している。(尤も、この体制は現時点では大幅に変更されている。)
CDMAの事業化は、米国よりも一足先に香港で始まり、韓国が「国を挙げての統一標準」としてこの技術を採用したことによって勢いがついたが、日本での事業化は、1998年に京セラ系のDDIが関西地区で始めたのを嚆矢とする。開業日にバッテリーが瞬く間に上がってしまうという大問題が発生し、関係者全員真っ青になったが、原因はすぐに分かり、クアルコムの技術者が一週間不眠不休で解決に取り組んで、何とか事なきを得た。半年後にトヨタ自動車系のIDOが関東、東海地区でも営業を開始し、やがて全国網が完成、次第に存在感を示すに至った。
しかし、データ通信がそれ程重要でなかった当時としては、CDMAのメリットは、「周波数の利用効率の良さ」だけだったから、さして周波数が逼迫していたわけではなく、多額の金を払って競り落とす必要もない日本では、当然のことながら大いに苦戦した。「音質が良い」という若干のセールポイントはあるものの、その程度のメリットだけでは、「コスト高」という致命的なデメリットを吸収出来るには程遠い。クアルコムは「ロイヤリティーが高い」「チップの値段が高い」と責めたてられ、毎日「針のムシロ」に座わらされているような感じだった。
しかし、もしDDIやIDOが、この時、直接の競争相手であるドコモが開発したPDCにとどまっていたら、常に「新しい機能を入れた端末はドコモからしか出ない」状態が続き、日本の携帯通信サービスは「見せかけだけの競争」にとどまってしまっていただろう。DDIやIDOのこの時の決断と、それに続く長年の忍耐は、日本の携帯電話業界に「真の競争」を持ち込む礎を築いたと、私は今でも考えている。
携帯通信のデジタル化(第二世代)の動きを世界的に俯瞰してみると、欧州全域を一つのシステムで一気に統一したGSMが、次第に圧倒的な強さを示めすに至った経過がよく見て取れる。
ノキア、モトローラ、エリクソンの三大メーカーが量産効果を生かして安くてスマートな端末を供給し、殆ど全世界でローミングが可能なGSMは、アジア、アフリカを席捲、米国の裏庭である中南米でも次第に優位に立った。アメリカでは、CDMA、北米標準のTDMA、それに米国政府自身が欧州から招きいれたGSMの三つの技術の鼎立となっていたが、そのうちにTDMAが没落した。技術的にはGSMより優位だったCDMAも、北米でこそ市場の半分程度を押さえたが、韓国と日本を除くアジアと中南米ではGSMに勝てなかった。日本固有のPDCは、日本の外では一勝もあげられなかった。
第三世代携帯通信(3G)事業を巡る角逐 (1999 - 2000年)
そのうちに2GHz帯を世界の統一周波数とする「第三世代モバイル通信システム(3G)の導入」が世界の通信事業者の関心を引き始めた。
ドコモは、「クアルコムが開発したCDMAは狭帯域だが、これをより広帯域で使うWCDMA方式の技術開発については、自分達が世界で最も進んでいる」と公言して、このシステムの世界標準化の先頭に立った。これに呼応したのが北欧勢のエリクソンとノキアであり、異なった方式を推すアルカテル(仏)とシーメンス(独)の連合軍と戦った。この戦いは有利に進んだが、ここで、思いがけず、CDMA技術の基本特許を持つクアルコムの頑強な抵抗に会う。
クアルコム側は、「音声とデータを広帯域の中で同居させるWCDMA(R99)方式には殆どメリットがなく、それはそれでよいとしても、取るに足らぬIPRを無理やりに導入してCDMAの基本特許の価値を薄めるやり方は不公正だ。世界中の巨大通信事業者と巨大メーカーが結託して小さなクアルコムを圧殺しようとするなら、あくまで戦う」という立場を貫いた。実際に「公正な条件が認められないなら、誰にもCDMAの基本特許の使用を認めない。その為にCDMAが世界標準にならないのなら、それでも良い」という爆弾宣言をして、世界中を驚かせた。
私は、サンディエゴの本社でこの方針が決定された現場に居合わせ、意見を求められたので、積極的な賛成論を開陳した。「ドコモは旧方式に回帰しないか?」と聞かれたので、「ドコモは技術的信念を曲げない会社故、それはあり得ない」と明言した。
この爆弾宣言は直ちに世界中に伝えられたが、日本では、私自身がドコモの立川社長や郵政省(当時)の稲田移動通信課長に伝えた。当然のことながら、関係者は全員が極めて不機嫌になり、私としては、決して楽しい経験ではなかった。その後、ドコモ(森永副社長ー故人)とクアルコム(ジェイコブス会長)は密かにパリで会見し、平和的な解決について合意したが、私は勿論それにも同席した。
クアルコムのこの強気の姿勢には、当然それなりの理由があった。クアルコムは「バースト型のデータ通信は電話とは全く性格の異なるものであり、それ故に、無線通信の方式も全く異なるものであるべきだ」という基本的な考えを持っており、既にデータ通信に特化した新しい方式を開発しつつあった。この方式は当初はHDRと呼ばれていたが、これが後のEVDOとHSPA(WCDMA方式の拡大版)の原型である。
このように、クアルコムは「携帯電話の将来像は携帯インターネットであり、その為にはHDR方式の早期導入が必要。方式を抜本的に変えないままに周波数帯域のみを広げて凌ごうとしているWCDMA方式は回り道である」と考えていたので、盟友である筈のKDDIが、第三世代に移行するに当たってHDR路線をとらずにWCDMA方式を選ぼうとしている事態に直面した時には、これに強く反発した。ジェイコブス会長も自ら稲盛会長を説得しようとしたが、うまくいかなかった。
クアルコム本社が極度に苛立っているのを感じた私は、遂に「伝家の宝刀」を抜くことを決意した。「KDDIが路線を変更してくれないのなら、クアルコム自身が日本で通信事業者となるべく、ライセンス取得競争に参入する」と宣言、その為に「ワープ・コミュニケーション」という企画会社を作った。その背景には、当然のことながら、米国の某大手通信事業者が日本進出に多大の興味を持っていたという「裏の事情」もあった。
この突然の宣言に、「三つの周波数枠を既存事業者三社に与える」という方針を既に内々で決めていた郵政省(当時)は仰天した。「まさかそんなことは出来ないだろう」とも思ってはいただろうが、私は、強い信念を吐露した「趣意書」を先行して郵政省(当時)に提出し、その中で「事業化の手順」までをきちんと示すことを怠らなかったし、米国大使館やUSTRの支援も得ていたので、あまり馬鹿にも出来なかったと思う。しかし、郵政省以上に事態を憂慮したのは、合併してKDDIを創ることに既に合意済みだったDDIとIDOだっただろう。
私は、生涯を通じて常に労を惜しまずよく働いたと思うが、一番集中して働いたのは、やはりこの時だったと思う。賽を投げてしまったのでもう後には戻れない。腰砕けになったら天下の笑い物になる。しかし、逆に免許が取れてしまったら、人集めから金集め、「データで勝負する新しいビジネスモデルの確立」まで、全てを一から始めなければならず、心身ともボロボロになるまで働き続けなければならなくなるだろう。
本心ではKDDIに翻意して欲しかったし、このことを公然と明言もしていた。その為に、私の行動を「所詮はブラフなのだろう」と思っていた人も結構いたようだったが、まさかそんな甘い考えでこんな大勝負は出来るものではない。私は、最後まで「和戦両様」の構えで事に当たっていた。
時間も切迫していた。わずか5人のチームで、日常の仕事をこなしながら、厚さ5センチ以上もある申請書類を1ヶ月足らずで作り上げたが、その間は、疲労と心労で毎日腹具合がおかしかった。米国の某通信事業者とは、投資の条件とその手順を含め、特に緊密な連絡を取る必要があったが、アメリカに行っている時間はなかったので、本社の支援を受けながら、殆どのことを電話会議でこなした。「午前1時頃まで書類作りをして、それから近くのホテルに泊まり、明け方の4時に目覚まし時計で起きて電話会議に臨む」というようなこともしばしばだった。
結果的には、稲盛さんが土壇場で方針を転換してくれたので、「ワープ・コミュニケーション」が事業会社として日の目を見ることはなかった。KDDIの最終方針はサンディエゴでのトップ会談で固まったが、その時点で、稲盛さんは、「ドコモの強力な技術陣に対抗する為に、クアルコムをKDDIの研究開発部門と考え、両者が緊密に連携する」ことをクアルコム側に提唱し、その場で合意がなされた。
「クアルコム・ジャパン」の仕事 (2000 - 2005年)
これで私は大きな重荷から解放され、普通の日常に戻ることが出来た。この頃になると、「クアルコム ジャパン」の社員数も順調に増え、会社としての体裁も整いつつあった。
その頃には、アナリスト達の主催する講演会などにも招かれることが多くなったが、そういう場では、私はいつも、「やがて携帯通信事業者のデータ収入は音声収入を凌駕する。それ故、データ通信に向いた新技術を一足先に使える立場になったKDDIが、近い将来ドコモを抜く可能性がある」と語った。「3Gライセンス取得宣言」で世の中を騒がせた直後だったので、「大ボラとしても面白い」と思ってくれた人は、結構多かったと思う。
(今になって、「KDDIがその時点で世界の大勢となりつつあったWCDMA路線をとらなかったのは失敗だったのではないか」と言う人がいるが、私はそうは思わない。「何れは全てのシステムが統合されていく」事は分かっていたし、それまでの間は、端末開発のスケールメリットに多少の差があっても「デュアルモードのチップ」で吸収出来る。しかし、時間は金では買えないから、この時点ではHDR(EVDO)で「データ通信での優位性」を誇示し、ドコモとの差別化を計る方が明らかに得策だったと、私は今でも考えている。)
広報活動のことについて触れたからには、もう一つ言っておかなければならないことがある。その頃の私は、CDMAのライセンス料を巡る日本の業界の反発に対しても、臆することなく立ち向かった。業界の不満はクアルコムのロイヤリティーが高すぎるということだったが、私は「さしたる根拠もなく高いと決め付けるのはおかしい。高いか安いかは需要と供給のバランスが決めるものだ。求められるものにはその価値があるのだ」と主張した。本社から出張してきた経営幹部は、この話になるとみんな逃げたが、私には「革新的な技術が生み出す価値」についての確固たる信念があったから、決して逃げることはなかった。
(私が退社してからずっと後になって、日本の公正取引委員会が、パナソニックの提訴を聞き入れて、「日本メーカーが不利な条件を受けることを『余儀なくされる』状況をつくった」としてクアルコムに排除命令を出したことを知り、私は心底驚いた。契約というものは当事者の自由意志によって為されるものであり、何者も契約を「強制」することは出来ない。「余儀なくされる」という日本語を英語に翻訳しても、全く意味をなさず、クアルコムは当惑して異議申し立てをしたと聞いている。この様なケースは世界でも例のない不思議なケースだったが、結局はパナソニックが提訴を取り下げて決着したと聞いている。)
ついでながら、かつての論戦の中では、私は公然とこう言っていた。「クアルコムはたまたま成功したが、その陰には、クアルコムの様に独創的な技術を追求して孤独な戦いを続け、遂に報われることもなく破綻していった多くのベンチャー企業がある。我々は、夢破れて散っていったこれらの人達の為にも、人々の羨むような大きな利益を上げなければならない。」
そしてまた、別の機会に、私はこうも言った。「日本の将来を担う若者達の為にも、我々は高額のロイヤリティーを取り続けなければならない。日本の若者達は、これを横目で見ながら、悔しさに耐え、『何時の日かは、自分があのようになる』と、闘志を燃え上がらせて欲しい。リスクを恐れ、人の後追いばかりしていては、結局報われることはない事を知ってほしい。」
クアルコム・ジャパンの仕事をしていて、嬉しいことも幾つかあった。
ある米国の機器メーカーが、本社のトップに対して、「クアルコムは日本法人の社長に幾ら払っているか知らないが、例え幾ら払っていたとしても。元は十分取れている」と言ってくれたこと。来日したチャイナユニコム会長の王建宙さん(その後チャイナモバイルの会長に転出)が、帰国後わざわざ本社のアーウィン・ジェイコブス会長に電話をして、「クアルコム・ジャパンのような会社を、中国にも是非作って欲しい」と言ってくれたこと等だ。
もう一つ嬉しかったのは、ベンチャー投資のささやかな成功だった。クアルコム・ジャパンは日本のスタートアップ企業を対象に30億円のベンチャー投資ファンドを運用する事を任されていたが、2年あまりの運用でその半分弱を使い、IPOにこぎつけた会社が4社、破綻したのは僅か1社で、これは本社を驚かす成果だった。若い時にベンチャー投資で全敗した苦い経験を持つ私としては、ささやかな成功であっても嬉しかった。
クアルコム・ジャパンの主たる仕事は、クアルコムのチップセットを買ってくれている日本メーカーを支援して、二つの目的を達成することだった。一つはKDDIの日本市場でのシェアを伸ばすのに貢献すること、もう一つは日本メーカーの海外市場での販売を増やすことだ。直接最終ユーザーに商品を売る立場ではないのだから、これが実現しない限りは、クアルコム・ジャパンの商売は増えない。
前者の鍵は、HDR(EVDO)を早急に導入して、データサービスのフラットレート化を実現することだったが、当時2兆円の有利子負債を背負っていたKDDIはなかなかその決断をしてくれなかった。HDRのインフラベンダーとしては、当時はサムスンと日立しかなかったので、日本ではまだ信頼が得られていなかった「サムスン」の売り込みに力を入れたのは勿論、「KDDIの大株主である京セラと日立との提携」も画策し、KDDIが一日も早く決断してくれるように、あらゆる努力を尽くした。
KDDIが「アイモード」で先行していたドコモとのデータサービスの競争で勝利する為のもう一つの鍵は、ゲームなどのネイティブ・アプリを携帯端末上で高速で動かす仕組みであるBREWの推進だった。
当時のクアルコムには、「BREWを拡充してリナックスのカーネル上で動くミドルウェアとし、先々は全体をリナックス OS化する」という構想もあったが、後にクアルコムは「多数のOSベンダーのそれぞれと緊密な友好関係を構築し、チップの拡販に注力する」という路線に進んだので、この構想は放棄された。これはクアルコムとしては正しい選択だったが、時計の針を少し元に戻して、もし早い段階でクアルコムが、先ずBREWを完全にオープンにして無償化し、その上で、各通信事業者が自由に格安で利用出来る「アプリケーション・ストア」を運営していたとしたら、世の中は相当変わったものになっていたような気もする。
また、当時のクアルコムは、未だに「GSM対CDMA」という対立の構図の中にいたが、早々とこの対立を解消し、BREWをGSM(GPRS)の上で動かしていたら、世の中はどうなっていただろうか?
クアルコム本社の上級副社長(Senior VP)に就任 (2005 - 2006年)
ちょうどその頃、クアルコム本社で私はシニアVPに昇格、日本と併せて東南アジア・大洋州を統括することになったので、これを機に、日本法人の社長を私より17歳若いパナソニック出身の技術者である山田純さんに譲り、私は会長になった。日本オフィスでは私は小さな部屋に移り、その代わりサンディエゴと香港にオフィスを持って、週末の殆どは国境を越えた移動に使う生活になった。
当初、私は、この新しい立場で、少しは日本の端末メーカーの海外市場開拓を助けられるのではないかと期待したのだったが、結局これは期待外れに終わった。
当時の日本メーカーは、世界市場で今よりはもう少し元気だった。三洋はアメリカのスプリント向けOEMでサムスンとほぼ互角に戦っていたし、クアルコムの端末機部門を買収した京セラも、サンディエゴを拠点とする世界市場向けのオペレーションの拡大をまだ諦めてはいなかった。「写メール」で世界に名を馳せたシャープには、欧州市場での販売拡大が期待されていたし、NECもクアルコムとのそれまでの確執を解消して、中国市場で攻勢に出ようとしていた。
クアルコム本社での会議では、日本を代表する私は、先進的なアプリケーションの分野では出席者の興味を惹くような面白い話をする事が出来たが、チップ販売の実績となると韓国法人と比べて見る影もなく、いつも悲哀をかこっていた。だから、日本メーカーに頑張ってもらって、何とかこの事態を打開したかった。
しかし、GSMが圧倒的に強く、CDMAは値段を安くしなければ売れない「東南アジア市場の現実」を見せつけられた私は、「これは一筋縄ではいかない。端末機もアプリも、コストの感覚を根本的に変えなければならず、しかも、長期戦を覚悟して忍耐強く取り組まなければ、突破口は開けない」と感じた。そして、それ以来、日本の端末メーカーに対する過度の期待は捨てた。
一方では、昔懐かしい東南アジアにしばしば足を運んでいると、私には商社時代の感覚が戻ってきて、色々なアイデアも浮かぶようになってきた。トップから頼まれたMediaFLO(クアルコムが開発した携帯端末向けの放送システム)関連の仕事以外では、日本のことは次第に私の関心外になっていった。
(MediaFLOについては、「地上波サイマルキャストの無料ワンセグに、ロングテールを狙う有料のクリップキャストを組み合わせれば面白い」と考え、ワンセグとのワンチップソリューションも用意したが、当初考えた「2年内の周波数取得」が不可能と分かり、断念した。先行したアメリカ市場は、私の考えでは、先ず無料サービスでユーザーの認知を高め、それから徐々に魅力のある番組を選んで、Pay-per-viewでビジネスモデルを作っていくべきだったと思うのだが、マーケティングを任せた通信キャリアーが始めから高い値付けをしたので、結局ユーザーにそっぽを向かれる羽目になった。これは、ノキアが力を入れていて欧州規格のDVBHでも同じことだった。)
本業となった「東南アジアでの安価なデータアプリの流通」を考えるにあたっては、私は取り敢えずインド人の技術屋と組んで、「広告と連動した音楽アプリの流通システム」を作り、「全ての発展途上国での同時多発的マーケティング」を画策した。この為、私は社内の組織の壁を破って、担当外のインドや中南米にも足を伸ばした。担当の東南アジアだけでは、何をするにしても市場が小さすぎたからだ。当初はハードに拘ったが、そのうちにハードは何でもよいと割り切れるようになった。
(クアルコムを退社した後で聞いた話では、私達が開発したこのシステムは、インド、中国、メキシコではある程度売れたらしいが、もともとの目標だった東南アジア市場とブラジルは駄目だった由である。)
しかし、私の最終目標は、この程度のものではなく、「第三世代の携帯電話機を徹底的に低価格化して、発展途上国全域に行き渡らせ、最貧国にまでインターネット環境をつくり、世界規模でのデジタルデバイドを完全に解消する」という構想だった。
そうなると、もう日本にいる必要もない。ここで、私は、「サンディエゴに生活の拠点を移し、3-4年間そういう仕事に注力した上で、70歳で引退する」という生涯計画を定めて、日本の関係者にもそういう挨拶をして回った。
孫正義さんとの出会い (2005 - 2006年)
ちょうどその頃に、孫さんからまた連絡があった。「また」ということは、以前にも色々な話があったということだ。孫さんとは以前から面識がなかったわけではなかったが、具体的に声がかかるようになったのは、彼が「どうしてもモバイルをやりたい」と考え始めた頃のことだから、2004年頃だったと思う。
私は、「孫さんは何れにせよモバイル通信に何らかの形で入っていくに違いない」と思っていたので、「そうなるとクアルコムにとっては見込み客先になるから、丁寧に対応しなければならない」とは考えていたが、その時点では、まさか自分自身がソフトバンクに入社することになるとは夢にも考えていなかった。
しかし、孫さんの人柄にはすぐに魅せられた。志やアイデアは夢中になって語るが、全て本気であり、回りくどいことは一切言わない。目一杯の「大風呂敷」は広げるが、偉そうぶるところは全くない。(私は、偉そうぶる人が嫌いだったから、この点が特に心に響いた。)彼と直接の接点を持ったことのない人達の中には、彼の「変わり身の早さ」を嫌って、「信用出来ない」と評する人も多いが、実際に身近で接してみると、基本的には率直で誠実な人であることが分かる。
私の方では、「将来の見込み客」だと思うからこそ、呼ばれれば出向いて、色々と意見具申などをしていたわけだが、彼の方では始めから全く社員と同じような扱いで、何の分け隔てもない。とにかく、何事につけ「目標と定めたことをやり遂げる」事だけが彼の唯一の関心事であり、その他の事には殆ど気は使わない。
そのうちに、或る時、「この人は本当に大きなことが出来る人かもしれない」と私は思うようになった。それは、私が彼の最大の長所と考える「拘りのなさ」を垣間見た時だった。たまたま私が出向いた時、彼は社員を前に自分のアイデアを熱っぽく語っていたが、それは、一言で言えば、良いアイデアではなかった。私が、たまりかねて、彼が見落としていたポイントを指摘すると、彼はしばらく考えていたが、すぐに「そうですね。そうかもしれませんね」と言った。そして、その場で、それまで熱をこめて語っていたアイデアをあっさりと捨て、全く違う角度からの議論を始めた。
人は誰でも勘違いをする。しかし、自分の誤りにある程度気付いても、大抵の人は自分のこれまでの考えを捨てきれず、或いは面子に拘る。この為に、転進のタイミングが一歩遅れる。しかし、孫さんは一瞬の躊躇もしない。勘のいい人であることは間違いないが、それ以上に、事実関係の把握を重視し、理屈に合わないことはやらない人だ。
「幾多の困難を乗り越えて彼がここまでやってこられたのは、恐らくこれ故だろう」と、私はその時に感じた。「この長点がある限りは、これからも大きく転ぶことはないのではないか」とも思った。(これは後々になって分かった事だが、孫さんにすれば、根幹の「理念」や「ビジョン」に揺るぎがなければ、戦術的な細部は如何様にも変わってよいということなのだろう。)
そのうちに、孫さんから「重要な話がある」と言われて呼び出されたので、出向いて話を聞くと、「1.7GHzの携帯通信事業のライセンスが取れるが、この分野に経験のある人が見つからないので、あなたがCEOとしてやってみてくれないか」という話だった。「この事業の為には、この程度の金は用意する」という話もあった。
私は、実はその直前に、当時のボーダフォンの英国本社の社長からも、「日本法人の社長をやってみないか」と誘われ、「自分は既に歳をとりすぎているし、とても自信がない」と断ったばかりだったから、この話もその場ですぐにお断りしようかと思ったが、それではあまりに誠意がないので、「一週間だけ考えさせてください」と答えた。
私が一週間貰ったのは、口先だけのことではなかった。投資額を含め、「もしこの条件が整えば」という答えぐらいは出さなければと思い、現実に色々な面をチェックした。しかし、幾ら考えても勝算はなかった。「既存事業者に地方でのローミングを義務付けることが出来れば何とかなるのではないか」とも考えたが、当時ソフトバンクは郵政省を相手取って訴訟までしていたから、「旧知の郵政省の高官に色々なことを打診して反応を見る」という事さえままならない状況だった。
結局、私は孫さんに会い、「私には全く自信がありません。しかし、孫さんもやられるべきではありません。このまま強行するのは自殺行為に等しい。孫さんは何時の日かNTTを超えるという目標を持っておられると聞きましたが、一度死んでしまえば、もう二度と戦えません」と伝えた。孫さんは目を大きく見開いて真剣に聞いてくれたが、最終的に、「あなたの言うことはよく分かったが、やはり、どうしてもやりたいなァ」と言った。
「これをやらないのなら、どんな代替案があるのか?」と尋ねられたので、私はこう答えた。「いきなり自分で一から始めるのではなく、ボーダフォンのMVNOをやることから始められたらどうですか? ボーダフォンは今のままでは立ち行かないが、ソフトバンクの販売力を利用すれば何とかなる。そのうちに彼等はソフトバンクを頼りにするようになります。そうなると、合弁に持っていけるかもしれないし、買収できる可能性もあります。仮にそうならなかったとしても、その頃には既に販売実績が十分出来ているのですから、この時にあらためて免許を取って、自分で全てをやることにしても遅くはない筈です。」
私は、その頃、実はボーダフォンの本社に対しても、「ソフトバンクをMVNOにすべき」という提言をしていた。来日した本社の社長と面接した際に「今度のクリスマス商戦にこれだけの端末を用意した。日本法人の社長は『これは必ず売れる』と言っているが、お前はどう思うか?」と聞かれたので、「申し訳ないが、私は全く売れないと思う」と答えた。
びっくりして理由を聞く相手に、私は、率直に、「見たところ日本のユーザーが全く魅力を感じない商品ばかりだ。『徹底的に日本のユーザーの気持になりきる』という姿勢がなければ日本では勝てない」と伝えた。そして「その解決策は?」と畳み込まれたのに対し、「本社の顔色ばかりを見ている日本人に頼っても駄目だ。中途半端なことはやめて、日本生え抜きのマーケティングのプロ集団に委ねた方がよい」と言って、ソフトバンクとのMVNO契約を奨めたのだった。
断れなかった再度の誘い (2006年)
それから約一年が経ち、私はまた孫さんから呼ばれた。「あなたのアドバイス通り、二兆円の大枚を払ってボーダフォンを買った。私は命を賭けてこの仕事をやり遂げる。この仕事は、『日本の為に』自分がやらねばならぬことだ。やるからには必ず成功させて、日本を変えて見せる。あなたも日本人なら、アメリカの会社の仕事などをしていないで、日本の将来の為に私のこの仕事を手伝うべきだ」と彼は言う。私は「二兆円もの借金をしてボーダフォンを買うべきだ」等とは言った覚えはなかったが、心の中では、「ここまで言われれば、とても断れない」と覚悟を決めた。
その決断に至るまでには、勿論、心の中に葛藤が全くなかったわけではない。既に「これからはアメリカに本拠を移す」と言っていたのに、日本に舞い戻るような形になるのは、何となくバツが悪い。多少煙たがられていたとは思うが、昨日までの盟友であったKDDIの敵に回るのも、少し心苦しくはある。収入面から言うなら、この時点でクアルコムを離れることは、相当額に及ぶ筈の将来のオプション株の権利をドブに捨てることを意味するのだから、普通ならあり得ない選択だった。
しかし、私にそれを乗り越えさせたのが、私の心の中にずっと蟠っていた「人生の最後は、矢張り出来れば日本の将来の為になる事をやりたい」「NTTのような『組織防衛優先』の保守的な巨大企業が日本の情報通信産業の中枢にいつまでも居座っているのは、日本の将来の為に良くない」という気持だった。
その頃のKDDIはドコモに対して一矢を報いつつあり、自分もそれには若干の貢献はしたという気持はあったが、この程度ではどうにもならない。しかも、そのKDDIも、私の目から見るとやはり大企業的な気風に染まっているように見えた。これに対して、「孫さんのような人なら、或いは本当にNTTの牙城を突き崩し、日本の情報通信業界を全く新しいものにしてくれるかもしれない」という秘かな期待が、私の心の中に芽生えつつあったのも事実だった。そうなると、もうお金のことは問題ではなかった。
私は商社マンだったから、それまでに多くのビジネスマンや経営者を見てきたし、伊藤忠を辞めた頃には、「久慈毅」というペンネームで、「人」の要素を重視する読み物仕立てのビジネス書を何冊か書いた程だった。だから、人を見る目はあるつもりだった。その目から見ても、孫さんが類稀な人であることは間違いなかった。絶え間なく考え、即座に実行するエネルギーは、常人の域をはるかに超えていたし、何よりも構想が桁外れて大きかった。
こういう人に、「自分は何としても日本を変えたい。だからあなたも手伝え」と言われて、これを断って日本を離れてしまったとすれば、後々までそれを悔やむことになるかもしれないと私は思った。
当初の話では、私の仕事は「技術部門の統括」という事だったから、いくら孫さんから「あなたはちょっと手伝うだけでよい」と言われていても、相当の覚悟をせざるを得ないと思っていた。ナンバーポータビリティー(電話番号を変えることなく、通信事業者を乗り換えることが出来る制度)の実施が秒読みとなっていたその時点では、下手をすればソフトバンクはドコモとKDDIの二社の草刈場になり、市場シェアを伸ばすどころか、15%強しかなかった既存シェアまで奪われて、破綻の危機に瀕する可能性だってないとは言えなかった。
私の見るところでは、後発で規模のメリットが取れない上に、第三世代システム用に使える周波数としては、使いにくい2GHz帯しか持っていないソフトバンクは、ドコモやKDDIに対して大きなハンディキャップを負っていた。買っている端末も、KDDIに比べれば押しなべてコストが高かったし、今後のデータサービスの展開についても、「技術戦略」というものが見当たらず、「職人技」によって対処するしかない体制のように見えた。
その頃の日本のビジネスモデルは、毎日既存顧客から入ってくる日銭を使って、高価な端末を只同然の値段で顧客に売る「サブシディー(販売奨励金)モデル」だったから、既存顧客の数が少なく、これからシェアを伸ばさなければならない後発事業者にとっては明らかに不利だった。ソフトバンクがマーケティングに長けていることは知っていたが、「技術部門で徹底的にコストを切り詰めて、端末価格の設定に或る程度の自由度を与えなければ、いくら強力な販売部門があったとしても、手の打ち様がなく、会社自体が立ち行かなくなるかもしれない」と、私は心の底から危惧していた。
そこで、私は、「この仕事を引き受けるからには、自分は誰に何と言われようと、技術部門の立場から『コストダウンの鬼』になる。それ以外には、この会社が生き残る道はない。もうこれが人生で最後の仕事だから、人に憎まれても、返り血を浴びることになっても構わない」と、悲壮な覚悟を決めた。健康診断を受けると血糖値が高いと指摘されたので、「完全に禁酒して、自分で自分に厳しい食事制限も課する」事も決めた。病気で倒れたら何も出来なくなり、恥を満天下にさらすことを恐れたからだった。
早々と「脇役」に転進 (2006 - 2007年)
しかし、入社して二ヶ月もたたぬうちに、私はこの「悲壮な覚悟」をあっさりと取り下げてしまった。
と言うのも、ボーダフォン買収からまだ4ヶ月しかたっていなかったのに、既に社内の体制は相当固まっており、全てがソフトバンク流に(つまり、社長の陣頭指揮下で)進められていることが分ったからだ。「技術よりもマーケティングと販売を先行させる」社風も、良い悪いは別として、過去の実績に裏づけられた揺るぎないものであり、これに異を唱えるのが妥当かどうかも判断がつきかねた。(というよりも、「この時期にはその方が正しいだろう」という判断に、自分自身も傾いていった。)
誰が考えたのか、「割賦販売方式」という新しいアイデアも導入済みだった。この方式なら、既存顧客からの収入が少なくても、毎月の利益を犠牲にすることなく、顧客に安い端末価格を提供できる。「目からウロコが落ちた」というか、「コロンブスの卵」を目の当たりにしたような感じだったが、これで私の最大の懸念は解消された。現実に、当初の若干の試行錯誤の後で導入された「ホワイトプラン」と名づけられた価格体系は、巧みなTV宣伝と相俟って、瞬く間に顧客の支持を得た。
営業部門の「集中力」と「巧みさ」は想像をはるかに超えるものだったし、技術部門も想像以上に厳しくやっていた。何よりも感銘を受けたのは、徹底的に顧客の反応を意識したスピード重視の「対応力」だった。毎週の経営会議では、何事も中途半端には終わらせず、即戦即決で必要な手が打たれている。実力者の宮内謙副社長(COO)が、孫さんが苦手とする分野をきちんと補っているのも大きいと思った。
私の担当分野であるはずだった「技術戦略」という観点からは、「本来やるべきことがやれていない」という不満があり、苛立ちも感じたが、会社が当面ちゃんとやっていける限りは、これは「どうしても直ぐにやらねばならない」というものでもないかもしれないと考えるに至った。無理にやろうとすれば、あちこちで摩擦が起こり、プラスよりマイナスが生じる可能性もある。下手をして指揮系統が二重三重になれば、良かれと思ったことでも、現場に大きな負担と混乱を与えかねない。
結局、色々考えた結果、私は「無理に仕事はやらない」という道を選んだ。これは、当初の「悲壮感」とは正反対の極にある選択だった。
内心忸怩たるものがなかったと言えば嘘になるが、それが大人の判断だと思った。「本気で仕事をする」と言えば男らしく聞えるが、それは自分中心でものを考えた時のことで、「天の時」「地の利」「人の和」がなければ、「空回り」だけで済まず、全体としては実質的にマイナスが生じる恐れがある。流石に45年近くもビジネスの最前線に身をおき、いろいろなことを経験してきたお陰で、私にはそういうことはよく読めるようになっていた。
そこで、私は孫さんと話し、ソフトバンクの中での仕事についてはラインの責任は全て外してもらい、元々彼が求めていた「社長へのアドバイス」という仕事だけに徹することにさせてもらった。言い換えれば、「必要に応じて脇を固める」という程度の、極めて受動的な役割のみに甘んじることにしたのだ。
私はそれまでの数十年間、どんな立場におかれても、終始積極的に目一杯に行動してきたし、「結果に対して全責任を負う」という意識を持たずに仕事をしたことはなかった。だから、こんな事は生涯を通じての初体験だった。実際にそういう立場で仕事をしてみて、「こんなことをしていて本当に良いのか」と、相当複雑な心境になったこともある。しかし、そのうちに、「実は、これは、長年真面目に仕事をしてきた私に対して、天の神様が与えてくれた特別の『ご褒美』だったのだ」と思うようになった。
この様な気楽な(責任のない)立場での仕事は、或る程度の歳になれば誰もが求めるものだ。しかし、私のような性格だと、現実にはなかなかそうは行かない。孫さんのような「誰よりも早く、何でも自分でやる。それも徹底的にやる」という人の下でなければ、とてもこんな役割には甘んじていられなかった筈だ。
現実に、経営会議などでは、「もし誰も言わないのなら、自分が言わなければ」と思う事はよくあるが、こういう場合も、殆ど孫さんが先回りしてその事を言ってしまっている。殆どの事において、私と孫さんとは発想が驚くほど似ているとは思っているが、彼の方がパワーが格段に大きく、決断力や集中力(執念)も桁違いだ。思考や行動のスピードについてもそうだ。私も、それまでは、自分では「頭の回転も行動も相当早い方だ」と思っていたが、孫さんには遠く及ばない事を認めざるを得なかった。
彼の言う事には、私が「無理筋」と思うことも多々ある。しかし、「可能性が極端に低く。出来なかった時のマイナスがあまりに大きい」というもの以外は、私は特に反対しない事にしてきた。彼は、どんなに小さい可能性でも「徹底的に追求する前に諦める」のを大変嫌う。あらゆる可能性を洩れなく追求しようとするし、目標値は最後の最後まで常に目一杯高く保ち続ける。「放っておけば人は安易に流れ、低い目標で満足してしまう傾向がある」事をよく知っているからだろう。
こういうやり方については、「僅かな可能性も逃さない」という利点はあっても、仕事の効率は相当悪くなるから、私は必ずしも賛成ではなかった。しかし、孫さんは極めて勘のいい人だし、瓢箪から駒が出ることもあるから、強く反対するだけの自信が私にはなかった。私は若い時から上に迎合するのは大嫌いだったが、孫さんの場合は、不思議に、「ここで反対しないのは卑怯だ」と思うことが少なかった。
実は、今のこの時点で、「それでは、少なくとも、最低限、やるべき事だけはやってきたか?」と自問してみると、率直に言って、「少し不甲斐なかったのではないか」と思うところはある。例えば、ボーダフォンから受け継いだネットワークの弱さは目を覆うばかりだったから、「通信事業者の生命線であるネットワーク施設の充実にもっと金を使うべきだ」と、面を冒してまで進言しなかった事を責められれば、それについては一言もない。(尤も、会社は目一杯の借金を背負って発足したのだから、「グループの財務戦略の根幹を完全には理解していない自分が出しゃばって言えることではない」と思い、遠慮せざるを得なかったのも事実ではあったが。)
しかし、その時点でも、「まさかこんな仕事で高い給料を貰っているわけには行かない」ということだけは、私は少なくともきちんと認識していた。そして、認識したら必ず行動に移すのが私の信条だ。
そこで、私は孫さんと掛け合って、「給料の減額交渉」をした。私からは男らしく50%減を提示したが、受け入れられなかったので、その半分程度の減額で手を打った。「給料の減額交渉」等というものは恐らく前代未聞だろうから、その事が少し楽しくもあったが、それ以上に、それと引きかえに手に入る「自由」の方が貴重だと私は思っていた。
不完全燃焼の時間 (2007 - 2011年)
結局私は、入社翌年から取締役副社長を退任する2011年の6月までを、かなり漫然と過ごした事になる。しかし、結論から言えば、それでも結果的には大きな問題は起こらなかったので、「後で自分の無能と怠惰を激しく悔やむ」というような憂き目にはあわずに済んだ。
ソフトバンクに入社した時に私が心配した事は三つあった。
第一は、ネットワークの脆弱性、つまりソフトバンクの本来の狙いであったデータ通信の利用が大きくなった時にネットワークがこの負荷に耐えきれずパンクしてしまう事だった。これに対しては、私は極めて早い時点からWiFiでトラフィックをオフロードする事を提唱してきていたが、当時は世界の通信事業者でそんな事を考えているところはどこもなく、ソフトバンクの社内でさえ、理解を得られるにはかなりの時間を要した。しかし、やり出せば動きは速く、且つ徹底的にやるのがソフトバンクの強いところで、結果としてソフトバンクは現時点で世界随一の充実したWiFiシステムを運営していると思う。
第二は、大都市部でのネットワークのカバレッジの問題であり、特にビル内の対応が難しい問題だった。ソフトバンクはドコモやKDDIと異なり、大きなセルを構成出来る上に建物の内部への浸透性にも優れた800MHz帯の免許を持っていなかったので、本来なら却って開き直れる、即ち、外からビル内をカバーする事を最初から諦め、異なった方法を追求するべきである事は分かっていたが、ビルのオーナーは様々であり、これと言った決め手は最後まで掴めなかった。この問題は、今なお世界中の携帯通信事業者が抱えている深刻な問題だ。
そして第三は、端末の問題であり、これが当時としては最も大きな心配事であった。
日本は携帯端末に様々なデータアプリを搭載する事については、世界で最も進んではいたが、一つ一つのモデル毎に一つ一つ組み込みソフトを開発するやり方に固執していたので、ソフト開発費が恐ろしく高いものにつき、それが日本の携帯端末機が世界市場では全く売れない原因にもなっていた。この解決策は明らかで、携帯端末用のOS、又はOSに準じるものを作り、これを全ての携帯端末に搭載した上で、様々なアプリケーションのソフトウェアを誰にでも自由に作ってもらう事にすればよい。時あたかもLinuxが市民権を得つつあったので、先ずはLinuxのカーネル上に出来るものから少しずつ搭載していくしかないのではないかと考えていた。
しかし、そんな事は言うは易くとも行うは難い。それに膨大な開発費と時間がかかる。既に、潤沢に開発費を使えるドコモはこの方向に進んでいたし、逸早く各メーカーの端末の共通化を進めていた上に、クアルコムのBREWでBinary Runtime環境を広くソフトベンダーに提供する経験を積んできているKDDIにも、先を越される恐れが大きかった。「一体どうすれば、他社に後れをとる事なく、多くの機能を備えた高度な端末を安価且つ迅速に開発出来る環境が整えられるのか?」これを考え出すと、入社当時は眠れない夜が続き、時には絶望的な気持ちになる事さえもあった。
しかし、この劣勢は、アップルによるiPhoneの開発と、これに全てを賭けたソフトバンクの大胆な経営戦略のおかげで、結果的には完全にひっくり返す事が出来た。つまり、この関係で世界のトップを走っていたかに見えたドコモが、Limoと名付けられた新しい携帯端末用のOSの開発にもたついている間に、アップルは自社開発のiOSを搭載した画期的なiPhone端末を発表、世界の大勢を一夜にして激変させたのだ。
更に続いて、グーグルがAndroidと名付けられたOSを全世界の全ての端末メーカーに無償で提供する事を発表したので、世界の全ての端末メーカーは一斉にこれを利用する方向へと動いた。こうして、私自身を含め、日本の業界が色々に思い悩んでいた携帯端末のアーキテクチャー問題は、一気に異次元に進んだ。世界のプレイヤーのダイナミズムの前に、大胆な発想の転換が出来ず、或いはそのスピードが遅すぎた日本のプレイヤーの限界が、計らずも露呈されたのだった。
iPhoneについては、私自身は極めて複雑な感情を持った事を告白しなければならない。始めてこれを使った瞬間には、私は「ああ、ここまで作り込んでくれる会社が遂に出てきたのか」と驚嘆し、殆ど感極まった。しかし、この思いは、やがてじわじわと、言いようのない敗北感へと変わっていった。
思えば、その20年前、私はニューヨークでオフィス用の電話システムの為に色々な機能を考え、ここで惨めな失敗を犯した後も、何時の日かは日本メーカーと組んで、携帯端末でその雪辱戦を果たしたいと秘かに考えていた。しかし、何も出来ないでいるうちに、アップルはこの様な一桁も二桁も上の商品を作り出してしまったのだ。彼我の能力のあまりの違いに、私は言うべき言葉もなかった。
経営者としての能力についてもそうだった。私は若い頃から、いつも上を見て、「自分が経営者ならこうする」と考えながら仕事をするのが習い性となっていたし、後から考えて「自分ならもっとうまく出来た」と思う事も多かった。孫さんのやり方についても、勿論、自分自身の醒めた眼で批判的に見る事もあった。しかし、「ここぞという時の勝負の賭け方については、自分はこの人には遠く及ばない」という事を、この時にまた骨の髄まで思い知らされた。iPhoneという画期的な商品が出てきた時に、孫さんは一瞬にしてその可能性を看破し、迷う事なく、会社の全ての経営資源を一気にこれに賭けた。私では、あそこまで徹底した決断はとても出来なかっただろう。
国際業界団体への関与とネット社会への参画(2009年 - 2011年)
このように、本来の仕事であった筈の技術関係では、私は心の中に悩みを抱えるだけで、実際には何も出来ずに手をこまねいているだけの存在に成り下がっていたが、ソフトバンクの中には、私でも若干は役に立ちそうな「渉外関係」や「海外関係」の仕事もあった。特に、世界規模の携帯通信事業者の業界団体として急拡大を遂げつつあったGSMAでは、孫社長の身代わりとして私をボードメンバーにしてくれたので、ここではそれなりに活躍の場もあった。少なくとも、私が参加する前は殆ど発言する事もなかったアジアの事業者が、活発に議論をリードする様になったのは、私がもたらす事の出来た一つの進展であった様に思う。
競合する各社が一同に会して、共通の利益について語り合うこの様な場に参画する事は、私にとってもそれなりの刺激にはなった。しかし、それと同時に、「通信事業者のような巨大な企業体は、どうしても保守的な体質にならざるを得ない」という事も、嫌でも身につまされた。それも良い勉強と言えば良い勉強だった。
しかし、この様な仕事は、時にはたて込むこともあったが、基本的にはそんなに忙しいものではない。私はお金と時間を無駄にするのが嫌いなので、海外出張のスケジュール等はいつも相当ハードだが、この程度の事は昔に比べれば物の数ではなかった。だから、この間、「ご褒美で貰った」とも言えるこの相当に自由な時間を、私は自分でも気が引ける位気儘に使わせて貰った。対外的な言論活動もその一つだ。
ソフトバンクに入社するに当たっての私の期待の一つは、それまで自分の弱点として意識していた「インターネットビジネスへのより深い関与」だったが、その中でも「ネットメディアの成熟」が特に私の関心事だった。伊藤忠時代から情報通信関係のスポークスマンのような役割を担っていた私は、新聞やテレビといった既存メディアについてはよく分かっていたが、ネットメディアのあり方については、感覚的に全く理解出来ていなかった。
理解するには自分でやるのが一番だ。その観点から私はブログを書き出した。それも日記風の気楽なブログを書くのではなく、一週間に一度位の頻度でネット上に小論文を掲載し、場合によればそれをベースに「論戦」をする可能性も追求したいと考えていた。その後、硬派のブロガーとして人気のある経済学者の池田信夫さんの呼びかけに応じて、2009年の1月から、日本初のマルチブロガーサイトである「アゴラ」の立ち上げに協力することになった。
「アゴラ」の記事を書くに当たっては、会社に直接マイナスになるような事は流石に言えないが、「会社の立場をいつも代弁していなければならない」とは考えず、出来る限り「国」とか「ユーザー」の視点から語ろうと心掛けた。会社の広報部に気を揉ませない様には、それなりに気を使ったが、「いざとなれば、『ああ、あの人は問題があるので辞めて貰いました』と言えばいいじゃあないの」と、彼等には冗談を言っていた。
2010年の1月からは、孫さんの薦めに応じて、半信半疑でTwitterをはじめた。有名人である上に、お客商売であるソフトバンクの経営に全責任を負う孫さんが実名でTwitterをやる事には大きなリスクがあるが、それを敢えて始めた孫さんは矢張り只者ではない。
「超多忙の孫さんでさえやるのなら、時間の余裕もある自分はもっと真面目にやって然るべき」と思って始めた事だったが、やってみるとクセになる。ぶつ切りの短い時間を使えるTwitterは、一日十本ぐらい発信しても殆ど負担にならない。今となっては、むしろ生活のリズムになり、気晴らしにもなっている。ユーザーからの容赦ない批判の声が聞けるのは、仕事の上でも大変役に立つ事が分かった。
再び「ネットワークの理想像」を考える(2010年 — 2011年)
「70歳で引退」というこれまでの計画を、2009年の11月に70歳の誕生日を迎えた時点で、一年だけ延ばしたが、その最大の理由は、「2010年中にNTTの構造問題にいよいよメスが入れられる」事になっていたからだ。そして、この問題は、孫さんが民主党政権に売り込んだ「光の道構想」と、期せずして一体不可分のものになった。こうなると、私もその事で少しは忙しくなるのが当然だった。
通信ネットワークについては、物理的な伝送路のところだけは全体のシステムから切り離し、「国家インフラ」という考えを導入するべきだと私はいつも考えてきた。そうしてこそ、徹底的に無駄を排した「計画的な建設」ができる。更に全国の津々浦々まで既に行き渡っているメタル回線を光ケーブルに一気に変えるという大胆な手法をとれば、NTTとしても「メタルと光を並行して保守しなければならない」という負担から解放される事になり、膨大なコスト削減が可能になると考えられた。
どんな分野でも競争原理を働かせればうまく行くと思っている人達は結構いるが、これは現実を知らないからだ。通信事業というものは、元々は国家が独占的にやっていたものなのだから、自由競争が可能なところでは、旧独占事業体に非対称規制を課してでも公正競争を実現すべきだし、競争が無理なところでは、その逆に、むしろ意図的に独占体制を維持して、その代わり透明性を徹底すべきだ。そうしなければ、物理的な伝送路というボトルネック施設を現実に寡占しているNTTのみが雪だるま式に栄え、実質的な競争が死に絶える危険性もある。
国のネットワークのグランドデザインは、「現在の電話回線を全て一気に光回線に敷き直す事を基本にして、その上に多種多様な無線網を配備する」という骨太のものでなければならない。間違っても中途半端なものを作ってはならない。そして、その上で動く通信システムが「コントロールされたIP網(NGN)」であるべきは当然の事だ。「放送」も「広義の通信」のエコシステムの一部とみなされるべきで、「ユーザーの為に何が良いか」という観点のみからその分担範囲が決められるべきだ。その為にも、NTTやその他の通信事業者、更にはNHKや民放各局、CATV事業者等が、「お互いの既得権を認め合って遠慮しあう」というような事態は、決して許してはならない。
大体こういう事が、当時私が考えていた事であり、ソフトバンクが提唱した「光の道」構想もそういう考えをベースにしているという点では同じだった。私はNTTの人達には何の恨みもなかったし、私の知っている個々の人達の能力と真面目さには、常日頃から敬愛措く能わざるものを感じていたが、常に「組織防衛」を第一義に考えているかのようなNTTの姿勢には、私は全く納得できていなかったし、将来の日本の情報通信産業の全てをそのようなNTTの手に委ねてしまうのでは、心安らかでいられるわけもない。そういう訳で、「光の道」論争が騒がしくなってくると、私の心の中でも、ずっと以前から蟠っていたNTTとの対決意識が次第に蘇ってきた。
しかし、結論から言うと、「光の道」構想は、プロフェッショナルな議論の場が設けられる前に、結論を出さねばならぬ期限が到来し、従って「実質的には殆ど意味のない結論」でその幕を閉じた。要するに「大山鳴動して鼠一匹も出ず」だった。進め方が短兵急に過ぎた上に、「民主党幹部の政治力」だけに頼るかの様なアプローチでは、所詮は無理だったのだと言わざるを得ない。NTTの持つ巨大な政治力は、そんな単純で粗雑なやり方ではとても突き崩せるものではない。
かくして、「NTT自身の考えやケーブルTV業界の考え等も公の議論の場に出して貰って、何が真に日本の将来の為になるかを皆で真摯に議論する」という「私が長い間描いていた理想の姿」は、結局は「夢の又夢」で終わってしまった。途中からは私自身も殆ど諦めの心境になっていたが、それでも、こうして終わってみると、不完全燃焼による心の傷は相当深く残った。
福島の原発事故がもたらしたインパクト (2011年 — 2012年)
6月末でソフトバンクモバイルの副社長を辞める事を決めていた2011年の3月に、東日本大震災が起こり、福島で深刻な原発事故が起った。これがなければ、私の晩年はもう少し違ったものになっていたかもしれないが、この為に私の心境には大きな変化が生じた。一言で言えば、副社長退任の9ヶ月後の2012年の3月には、「仕事を始めて丁度50年になるからもういいだろう」という理由で実業の世界から完全に引退する計画だったのを急遽取り止めて、更に5年間、身体が続く限りは働く決心をしたという事だ。
東日本大震災だけなら日本は十分立ち直れると私は考えていたが、原発事故については「その影響は計り知れぬものがある」と思わざるを得なかった。それを考える時に私の頭に去来したものは、「戦慄」という言葉が当てはまる程のものだった。この事故の「原因」とその「影響」を考えると、「日本はこれまでの原発依存によるエネルギー政策を根本から変えなければならなくなるだろう」と私は素早く予測した。もともと国債の過大な発行残高に危惧を持っていた私は、「エネルギー政策の破綻」がもたらすかもしれない「財政破綻」の可能性に恐怖した。
ここで大人達がしっかりしなかったら、孫達の世代にとても申し開きは出来ない。しかし、何をどうすればよいのかは全く分からない。私自身は「原発」には反対ではない。放射能が生命体に与える影響に恐怖を感じる事については私も人後に落ちないが、それは遺伝子操作がもたらすかも知れない破局と五十歩百歩のものだ。そして、人間は既に核技術や遺伝子工学を弄び始めてしまっており、もはや後には戻れない。「科学技術に取り組んだからには、決して逃げてはならない。逃げれば、誰かが過ちを犯すのを防げなくなってしまう。恐怖に打ち勝ち、あくまで真正面から立ち向かって問題を克服するしかない」というのが、私の基本的な考えだ。だから、「反原発」の動きが過激になって、日本から原子力関連の技術者がいなくなってしまう事を、実は私は何よりも恐れていた。
しかし、その一方で、孫さんの「原発」に対する恐怖心は本物のようであり、この為に、彼はかなり過激な「反原発」の姿勢を取った。どんな時でも抽象的な議論に終わらず、必ず具体的な代案を出し、これを直ぐに実行に移すというのが彼の真骨頂だ。だから、この時も彼は直ちに「自然エネルギー導入」の旗印を掲げて、大胆なメガソーラー計画等をぶち上げた。この頃は、私は既に副社長は辞めていたが、取締役会の一員としては残っていたので、かなり辛い立場に置かれた。社長の方針はサポートしなければならないが、親交のある大企業の幹部などからは、ソーラー発電の高コストを指摘されて、「日本の経済を破壊しようというのか」となじられる。
そんな時に、私はある人の紹介で東北大学の大見忠弘名誉教授とお会いする事になった。「太陽光発電に情熱をかけている孫さんは立派だが、今のコストではどうにもならない。2年間待ってくれたら、私がコストを3分の1に下げてみせる」と言っておられた由で、孫さんに会いたいとの事だったが、孫さんは多忙でとても会えないし、そのまま握り潰す訳にも行かないので、私が代わりに仙台まで出向く事にした。
大見先生にお会いしてみると、73歳の高齢にも関わらず情熱の固まりの様な方で、「現在の半導体製造技術が向かっている方向には科学の原理原則に反するものが多く、本質的に誤っている」と激しい事を言われる。半導体製造に不可欠なクリーンルーム開発の父と言われる「実績」に加えて、数えきれない程の「受賞歴」も持っておられる上に、過去10年間で文科省と経産省が何と総額400億円もの金額を先生の研究に注ぎ込んでいた事が分かった。こうなると、私も先生の言われる事を真剣に受け取らざるを得ない。しかも、この膨大な資金を使って、先生は民間企業が羨む様な高価な試験機等を自らの研究室に備えておられたのだから、これが役に立たないわけはないと私は思った。
半導体技術の本質的な問題はよく分からなかったが、シャープ等が手掛けていた「薄膜方式の太陽光発電システム」の光電子転換効率を3倍にして、生産性も上げるという大見先生の構想については、具体的な機器の設計も生産コストの計算も既に出来ていた。6億円程度の研究資金さえあれば、パネル製造を手掛けるメーカーが納得する様なサンプルを半年程度で作り上げてみせるとの事だったので、私も眼を輝かさざるを得なかった。太陽光発電システムの中でパネル自身のコストが占めるのは約半分程度だが、周辺システムのコストダウンには色々なアイデアが出てくる可能性は十分あったから、本当にこれが実現すれば、日照量の多い米国や中近東では、石油や天然ガスによる発電よりも安いコストでの太陽光発電が可能になる事を意味した。
私は元々「ドイツや北欧諸国のように環境意識の高い国が、国民の税金で自然エネルギーへと転換するのは、自己満足以外には殆ど何の意味もない」という考えだった。一部の先進国がCO2の排出を抑制したところで、中国やインド、ブラジルや東南アジア諸国といった「人口が多く、且つ国民の生活水準の急速な向上が予測されている地域」での自然エネルギーへの転換が進まなければ、地球規模で考えれば、実際には何の役にも立たないからだ。しかし、こういう地域では、太陽光等による発電コストが化石燃料によるものより安くならない限り、そんな事は簡単には起こらない。だから、自然エネルギー問題は「技術革新によるコストダウンの可能性」が問題の全てであると私は考えていた。
大見先生によれば、シャープ等による薄膜方式のエネルギー転換効率が低いレベルに留まっているのは、アモルファスや微結晶状態にあるシリコン化合物の中から水素原子が離脱し過ぎているからであり、プラズマ励起領域と反応領域を切り離して、全てのプロセスを低温で安定した状態に保てば、この問題は解決出来るとのことであり、「金属表面波という微弱な電波を使って広範囲に均一にプラズマを励起することを可能にした新しい設備」の能力に大きな期待がかかっていた。しかし、6億円程度の金が直ぐに手当出来なければ、この為の試験設備は導入出来ず、それどころか、研究所自体の運営が明日にでも行き詰まりかねないという状況だという事だった。
時あたかも民主党政権による「事業仕分け」が脚光を浴びている時代で、スパコンの開発資金も槍玉に上がっている状況だったので、国からの資金拠出はもう期待出来ない。「この様な構想が資金難の為に行き詰まっている」という事実を知る前ならよかったのだが、一旦知ってしまった以上は知らないふりをする訳にも行かない。そこで私は一大決心をする。「最早原発には依存出来ない」そして「自然エネルギー問題の抱える本質的なジレンマ(高コスト)は、技術開発(特に半導体技術)でしか解決出来ない」と考える限りは、「この構想の存在から眼を背ける事は、自分自身の存在意義を自ら否定するに等しい」と思い詰めるに至っていた。
いい歳をして、再び「手痛い挫折」を味わう(2012年 – 2013年)
そこで、私は孫さんと掛け合い、ソフトバンクだけではとても賄いきれないので、昔から親しかった古巣のクアルコムのCEOであるPaul Jacobs博士にまで頼み込んだ。このような「当たるも八卦、当たらぬも八卦」と言ってもよい様な開発案件に人様を巻き込むのに、自分ではリスクをとらないというのは筋違い故、個人的にも身の程以上の拠出(出資)を覚悟した上、「生涯無償でこの事業の推進を引き受ける」という決意まで吐露した。
これには勿論別の背景もあった。大震災に際して、孫さんは自ら個人的に100億円を寄付して世の中を驚かせた。だから、私の個人資産は孫さんの1万分の1にも満たないにしても、私自身も「何かはやらなければならない」とは思っていた。そこで、「お金ではなく、リスクの負担と自分の時間を使う事で、自分としてもささやかながら貢献しよう」と決心した訳だ。「これで東北大学の名前を世界に轟かす事が出来れば、東北復興の一助にもなろう」という考えも、勿論その根底にはあった。
当然の事ながら、ソフトバンクの役員は全員反対だった。「そもそもソフトバンクは、その成り立ちからして、基礎技術に投資する会社ではない。松本さんは役員でありながらそんな事も分からないのですか?」という訳だ。私にすれば「グループの総帥である孫社長の反原発運動が経済界で不評なので、これに対して一矢を報いたいという意味もあるのですよ」と反論したいところだったが、そうも言えない。
結局は、自分でも恥ずかしい位の「ゴリ押し」で、不承々々認めて貰うしかなかった。クアルコムの方は「今後は半導体製造技術の方まで踏み込んでいくべきでしょうから、日本で最先端の研究拠点と繋がりを作っておいてもよいのでは」という大雑把な話だけで、何とか認めてもらった。それぞれ2億5000万円の出資だ。かくして「スーパー・シリコン・テクノロジー」という名前の新会社が、私が社長を引き受ける事によって、難産の上に設立された。
しかし、世の中はそう甘くはなかった。試験機を導入して悪戦苦闘する事半年あまりで、多くの推測に誤りがあった事が分かった。半年である程度のサンプルが作成出来れば、当時はまだ蜜月関係にあった台湾の鴻海グループの会長が個人的に出資していたシャープの堺工場にこれを持ち込んで、プロジェクトを次の段階に進める予定だったのだが、とてもその状態には程遠かった。「多くの問題を抜本的に見直した上で、更に一年から二年かけてやっとある程度のものが出来る」という状態では、資金はとても続かない。そもそもソフトバンクやクアルコムにはこれ以上は一切負担をかけないというのが当初からの約束だった。
私とて、長年実業の世界にいたので、いくら「生涯をかけての国の為の仕事」と意気込んでいたからといっても、物事が期待通りに行かない場合のフォールバックプランを持っていなかった訳ではない。この場合には、この研究所が所有する300件を越える半導体製造関連の特許を切り売りして、2年間位は糊口を凌げるという計算はあった。(尤も、その為には、既に自民党政権が国立大学に対して拠出する事を決めていた産学連携の開発資金を獲得する必要があり、この為には一定の形式要件を整える必要があったのも事実だったのだが。)
しかし、ここで、考えてもみなかった更なる悲劇に私は見舞われる。この仕事を始めるにあたり、特に特許を切り売りして糊口をしのぐ事を想定した場合に、私が最も頼りにしていた田中信義さんが、68歳の若さで膵臓癌で急逝されたのだ。元々東北大学で半導体の研究をしておられた田中信義さんは、キャノンで専務まで勤められた後、退職して特任教授として東北大学に戻られていたが、政府の知的財産戦略推進本部の委員を務められる等、知的財産の分野では日本の最高峰におられた方だった。だから、私から特にお願いして、新会社の副社長になって頂き、特許戦略をお委せしていたのだが、この方を失ってしまっては、私だけで特許ビジネスをやっていく事は難しいと考えざるを得なかった。
一方、ソフトバンクの財務担当者に状況を説明すると、「ソフトバンクとしては、あくまで太陽光発電技術に対して投資したのであって、この会社が幅広く半導体技術を対象とする事は想定していない。それよりも、太陽光発電関係で当初の目論が実現出来る可能性が当面見出せないのなら、会社はすぐに全ての活動を停止し、残存財産を株主に払い戻すべきだ」との回答。こう言われれば反論は出来ない。クアルコムはソフトバンクの意向に従うという立場。その上、大学側も、今後の支援体制については一向にコミットしてくれず、「産学連携」の理想と現実のギャップは覆い隠すべくもなかったので、こうなると私には最早どうする事も出来なかった。結局、私は、涙を呑んで会社の解散を決定するしかなかった。
この間、私は眠れない夜を幾晩も過ごした。若い時に起こしたベンチャービジネスが破綻しつつあった時に見た悪夢の再来だった。結局、全ての成否は「技術的なアイデアの実現可能性」の如何にかかっていた訳だったから、その判断が甘かったと言われれば一言もない。「だから、言ったでしょう。松本さんもいい歳をして、相変わらず甘いんですねえ」と言われれば、只々恥じ入るばかりだ。
しかし、これも私の人生の一こまだったに過ぎない。結局は「これからは生涯を通して無償で国の為に働く」という誓いが、脆くも挫折したという事だ。自分の不明からソフトバンクやクアルコムに損失を被らした事に対する恥ずかしさと負い目を除けば、私にとっては「只それだけの事」だった。
ソフトバンクの米国進出と自分自身の針路(2013年 – 2014年)
さて、「生涯、国の為に無償で働く」という誓いがもろくも崩れつつあった同じ頃に、私の回りでは異なった大きな動きも進んでいた。それはソフトバンクの海外戦略に関連する事だった。
ソフトバンクは元々日本に留まっている気などはさらさらない会社だ。日本で慣れない通信事業分野に進出し、格段の経験の蓄積と顧客ベースを誇るドコモやKDDIに挑戦するというのだから、少なくとも最初の5年間程度は日本市場での競争に専念せねばならないのは当然だが、市場シェアが確実に増えて20%を越え、なおも上位との格差を着々と縮めていく目処がたった時点では、海外に事業を拡大するのがこれまた当然の事だった。
大きな勝負手を一気に打つのが身上で、細かい布石の積み上げにはあまり興味がない孫さんとは異なり、私は「人があまり興味を示さない時に、分からないところで秘かに布石を打っておく」という様な仕事が好きだ。これは性格なのでどうにもならない。
この時点で私が眼を付けたのは、巨人インテルが技術開発と市場開発に躓き、インテルを信じてWiMAXという無線通信の新技術に大きな投資をしてきた人達を後に残して、早々と退場してしまった空白地帯である。実はクアルコムで経験を積んできていた私自身は、当初からWiMAXの技術的な問題点はある程度分かっていた積りだったので、これが挫折した時には正直に言ってむしろホッとしたような気持の方が強かったのだが、「WiMAXの挫折で宙に浮いた膨大な量の周波数をどうするのか」という現実的な問題を考えると、じっとしていられなくなった。
「何時でも何処でも電話ができるし、何処にいようともかかってくる電話を逃す事はない」という「只一つの超強力なキラーアプリケーション」のお陰で、「携帯通信というシステム(かつては自動車電話と呼ばれた)」はあっという間に世界中で膨大な市場を作り出したのだが、この頃になると「電話」や「ショート・メッセージ」の市場は既に世界中で飽和状態になりつつあり、これに代わって「何時でも何処でもあらゆる種類のインターネットサービスにアクセス出来る」という事に対する人々の欲求が、徐々に顕在化しつつあった。これこそ「パラダイムシフト」だった。
しかし、携帯インターネットとなると、これに必要とされる周波数の量は電話とは比較にならない。それだけの周波数を持てるかどうかが、これからの競争では成否を決める鍵になるのではないかと、私は考えていた。そうなると、これまでに世界中でWiMAXを対象に与えられた周波数免許の事を考えない訳には行かない。インテルから見捨てられた世界中のWiMAX事業者は茫然自失して将来を見通せない状態だったが、時あたかも既存の携帯電話技術の延長線上で開発されていたLTEという新技術を使えば、WiMAXと全く同じ周波数をもっと効率的に使える事が分かっていたから、私はそこに目を付けた。未使用のまま放置された周波数は遠からず国に取り上げられる。その前に手を打つ必要がある。急がねばならない。
しかし、周波数があるだけでは勿論事業にはならない。既に隆盛を誇っている既存の大手携帯電話事業者の一角に食い込むには、これまでになかったビジネスモデルを考え出し、強力なマーケティング戦略で新しい需要を引き出さなければならない。それはそんなに容易な仕事ではないが、それ故に私は久しぶりに闘志を燃やした。
たまたま接触のあったインドネシアのWiMAX事業者が、「事業の継続か断念か」の瀬戸際に立っていた事が分かったので、私はその事業を持つインドネシア有数のLippoグループの総帥と会い、孫さんに引き合わせた。二人は意気投合し、共同で新しい事業を進める事になったので、私は新しいビジネスモデル作成の鍵となる技術をあれこれと模索した。しかし、その時に米国第三位の携帯通信事業者であるスプリントを買収しないかという話が突然ソフトバンクに持ち込まれ、孫さんは電光石火「米国への本格進出」を決めた。
こうなると、もうアジア諸国で小ぶりの通信事業にかまけているわけにはいかない。結局ソフトバンクの通信事業部門は、当面は脇目も振らず米国での事業推進に全ての経営資源を集中する事になった。インドネシアでの事業については、孫さんが先方に対して「この事業は成功すると信じているが、諸般の事情からソフトバンクとしての投資は出来ないので了承してほしい。後は松本と相談して欲しい」と伝えていた事もあり、私は自ら願い出て、個人の資格で、引き続きこの事業の成功を見極める道を選んだ。
スプリント買収の話は突然持ち込まれたものだったが、私も意見を聞かれたので、即座に諸手を上げて賛成した。この会社の過去を私はかなり良く知っており、その数年前までは「最も近づいてはいけない会社」と位置づけていたが、この頃になると、やっと正しいネットワーク戦略に焦点が定まって来ていたようだったし、「今ならやりようによってはベライゾンとAT&Tという二大巨人に肉薄することも可能ではないか」と考えるに至っていたからだ。
一旦方針が決まると、その方向へと会社全体が脇目もふらずに走りだすのがソフトバンクの文化だ。この頃には既に通信事業者の経営幹部として恥ずかしくないレベルに育ってきていた若い人達は、孫さんの強い意向で、日本と米国の両市場を一体として考える事を求められていた。私自身としても、米国市場を攻める戦略については若干の思いもないではなかったが、こういう状況下では、過去の人間が会社の本流のところで中途半端に口を出すのは憚られたから、「出しゃばる」のはやめた。
それに、もし米国市場の攻め方を本気で考え始めたら、少なくとも4-5年の間は、その事ばかりを昼も夜も考え続けていなければならない。こうなると昔から興味のあった「発展途上国での新しいビジネスモデルの開拓」も出来なくなるから、何れにせよ、ここで「出しゃばる」理由は全くなかった。
ジャパン・リンクで最後の挑戦(2014年 - )
この時点で、私はソフトバンクモバイルの副社長はとっくに辞めていたし、その一年後には取締役も辞めていた。しばらくは、特別顧問というタイトルの役員待遇で、執務室や秘書も使わせてもらっていたが、中途半端な立場で会社の中をウロウロしているのは良くないという思いもあり、伊藤忠をやめた時に創った自分自身の会社である「ジャパン・リンク」を15年ぶりに復活させ、2014年の4月からは、オフィスも新しく構えた。ソフトバンクでの特別顧問というタイトルは変わらないものの、契約形態は雇用契約ではなく業務委託契約になった。前述のインドネシアの会社との個人契約も、ジャパン・リンク経由に切り替えた。
「ジャパン・リンク」は一応何でも出来る会社にはしてあるが、さすがにこの歳になると、コンサルタント的な仕事以上の事はできないと思っている。「若い人達と語らって、インターネットがらみで新しいサービス事業を起こす」等という事にも、今なお魅力を感じないわけではないが、途中で病気になったり、死んだりしたら、一緒にやってくれていた人達に大変な迷惑をかけることになるので、これだけはやってはならないと自戒している。
しかし、コンサルタント業と言っても、私の場合はどうしても「真剣勝負」になる。私を頼りにしてくれた会社に対しては、何としても「結果を出す」事で報いたいからだ。そして、結果を出そうとすれば、その会社を「自分の会社」と考える事が不可欠だ。そうなると、何の事はない、経営陣の一角に入ったのと、精神的には全く同じ事になる。自分のアドバイスが悪い結果を招く事になれば、単に「恥ずかしい」では済まされず、長い間責任感に苛まれる事になる。
約半年で、ジャパン・リンクが結んだコンサルタント契約は、大小取り混ぜ合計9件になったが、対象としては、殆どが長年やってきた携帯通信分野の仕事であり、殆どが海外での事業展開だ。「前途の見通しに不安を持っているWiMAX事業者に新しいビジネスモデルを推奨し、一緒にこれを立ち上げていく」事を当面の最大の目標にしているが、やっていると「新しい通信事業のあり方はかくあるべし」という大きな構想へと、どうしても考えが膨らんでいってしまう。これを可能にするかもしれない新しい技術の可能性に気がつくと、矢張り興奮してしまう。
ソフトバンクを離れたとは言え、長年の恩義がある上に、顧問契約も継続して貰っているので、ソフトバンクのマイナスになる事は出来ないし、出来れば「回り回ってソフトバンクの為にもなった」という結果が出せればと考えている。しかし、日本とアメリカを除けば、ソフトバンクと競合する可能性ある会社は少ないので、この事はあまり負担にはならない。何よりも、自由に発想し、自由に行動出来る嬉しさは、かけがえのないものだ。
インドネシアの会社について、ソフトバンクが抜けた為に生じた投資額の穴を、私が考え出した「新しいビジネスモデル」を理解してくれた三井物産が埋めてくれた事もあり、ジャパン・リンクは三井物産とも契約を結んだ。久しぶりに世界の各地に拠点を持つ大商社と一緒に仕事をしてみると、やはり快適だ。伊藤忠を裏切ったというような気持ちは全くない。伊藤忠は昔も今も通信分野ではNTTとの関係を中核においているので、今となっては私とは何れにせよ接点に乏しい。この歳になってまさか伊藤忠と競合する三井物産の仕事をする事になるとは夢にも思わなかったが、これも長く生きていることの面白さの一つだと感じている。
こういう仕事を始めてしまったので、毎月の半分以上が海外だ。やはり東南アジアが一番多いが、サンパウロで仕事があれば、デュバイ経由にしてパキスタンと南アフリカに立ち寄るか、それとも米国経由にしてワシントンとサンディエゴ、サンフランシスコに立ち寄るか、最後まで迷う。テヘランに行った時には、旅費と時間がもったいないので、帰りにダッカ、シンガポール、ジャカルタでの仕事を入れた。一回の出張で五泊もしたのに、ホテルで寝られたのは二回だけ(あとは全て機中泊)というような強行軍もあった。
いい歳をして何故そこまで働くのかといえば、やはり仕事が好きだからなのだろうが、一種の使命感のようなものもないではない。特に携帯通信業界に関連しては、「自分以外には世界で誰もやらないだろう」と思われる仕事もあり、そういう仕事については、何とかして結果を出し、それを死ぬ前に自分の目で直接見たいという気持ちが抑えきれない。
それから、他のもう一つの理由もある。前述のように、私は、東北大震災の後に、「孫さんのように100億円は寄付できないが、自分の身体で払えるものは払おう」と思ったことがある。一生をかけて「半導体」と「産学連携」の為に無償で働こうとした決意は脆くも挫折したが、「少なくともあと5年は若者のように全力で働く」と公言した事は変えられない。
そもそも「日本の当面の高齢化問題は、高齢者がもっと働く事で当面は忽ち解決する」と私は常日頃から論じており(高齢者デノミ論)、「それなら、まず自分からそうするのが筋だ」と思っている。出稼ぎ労働者よろしく自分が外国の顧客から稼いでくる「ささやかな外貨」などは勿論物の数にはならないが、10万人ぐらいの高齢者が同じ事をすれば、日本経済も少しは良くなるだろうと本気で思っている。
(付記) 死ぬまでにやりたいこと
今や世界的な事業家の一人である孫さんとは異なり、ビジネスの世界では、私は所詮は小さな存在にしかなれなかった。
何にでも好奇心を持ち、色々なことをやってきた割には、まだ生き延びているのだから、運が良い方であったことは間違いないと思うが、残念ながら、自分自身の潜在的能力は、生涯を通じて結局は半分も生かせなかったように思う。しかし、それは、自分にガッツがなかったからだし、それにもう済んでしまった事だ。孫さんの「30年構想」のようなものを、私は元々全く持ち合わせていない。つまり、私は本当の意味での事業家ではなかったのだ。
しかし、その一方で、「人の一生というものは、もっと幅の広いものであるべきだ」という強い思いが私にはある。運よく80歳を越えるまで、頭もあまり呆けることなく生きられるとすれば、今手掛けている仕事は77歳を堺にして徐々に減らして、その後は、全く別の事に、自分自身の時間をもっと割きたいと思っている。
日本の将来への貢献という面では、「教育現場の改革」の為に役立つ事を何かやりたい。私は、常日頃から「今の大学教育のあり方はおかしい」とも思っている。特に興味があるのは、「国内外の若い人達に幅広い知識の吸収と交流の場を提供する事」だ。情報通信技術の活用がその為には欠かせない。こういう事は、既に先人達が多くのことを手掛けているが、自分もその中に飛び込んで何等らかの手助けをしたい。
そういった事も意識しながら、自分でも一つか二つ大学や大学院で講座を持ってみたいと考えていたところ、幸いにもご縁があって、明治大学専門職大学院のグローバルビジネス研究科長の木村哲先生からお声がけを頂き、20年の秋から同大学院の「特別招聘教授」を勤めさせて頂いている。自分で言うのも変だが、かなり情熱的な授業が出来ていると思うし、私自身の実体験に基づいた授業は、それなりに受講生の興味も惹いているだろうと思っている。この立場を手掛かりに教育問題にもっと深く関与出来れば、望外の幸せだ。
しかし、それ以上にやりたい事が私にはある。「やりたい」というよりは、「やらなければならない」事だと言ってもよいだろう。それは、自分の周りに謎めいて存在する「世界」と、不可避的にそれと関わっている「自分自身」を見詰め直す事だ。そして、それに近いところにあるものとして、私には「文学」がある。
私は、今から10年以上前に、「久慈毅」というペンネームで、読み物仕立てのビジネス書を3冊、ダイヤモンド社から出版して貰ったことがあるが、その後は「純文学」を志して、「外村直樹」という新しいペンネームで、既に、長編を2編、中編を8編書き下ろしている。「感性が衰えないうちに書き上げてしまわなければ」という思いで、長い年月をかけて、夜や週末に精力的に書き続けてきたものだが、中編1編をある文学雑誌に掲載してもらった以外は、全て未発表だ。
「外村直樹」の作品群の内容は、自分としては全て極めて哲学的なものであると思っているが、筆者の年齢から想像されるような「枯れたもの」ではない。それでも、その殆どが、ビジネスの世界での私とは全く無縁な「諦観」と「不条理」がテーマになっている。恋愛がテーマでも、この根底は変わらない。
ちなみに、人はよく「不条理」という言葉に特別な思いを込めて使うが、私は「この世界は元々『不条理』でしかあり得ず、『条理』が全ての根底にあると信じなければ生きていけないような人間には、自分はなりたくはない」と、密かに心に決めている。実は「その事こそが、私が今ここに生きている事の唯一つの意味であり、これだけはどうしても譲れない一線だ」とまでも思っているくらいだ。こういう本を普通に出版してもらうのは難しいが、電子書籍が一般化してハードルが下がれば、一括して世に問いたい。百万人に理解してもらう必要はない。例え数百人であっても、本当に理解してくれる人がいればそれで十分だ。
その意味からも、電子出版の市場拡大にも大きな関心を持っている。今は時代の転換期、全てが「双方向」の世界へと大きく動いている。これからは、同じような考えや感性を持つ老若男女の人達が、それぞれにネット上で自由に交流出来るようになるだろう。文学の世界も、一握りの出版社の商業主義のくびきから自由になり、昔の同人雑誌のようなみずみずしさを取り戻せるかもしれない。
あまりに気が多いので呆れられるかもしれないが、私は「歴史」の勉強にも強い興味を持っている。新しい技術は次々に出てくるのでもう追いきれないが、歴史の勉強なら過去の事を追うだけでよいので、そのようなプレッシャーはない。
特に、明治維新以降の日本とその周辺国の歴史は、もっと勉強したいと思っている。そして、その勉強の結果をベースとして、「日露戦争から太平洋戦争までの時代」を背景に、「仮想的な歴史大河小説」を書きたいと思っている。「日本がもし日露戦争に勝てていなかったら、世界の歴史は全く違ったものになっており、その中で日本はこんな国になっていたかもしれない」というのがテーマだ。
実際の歴史は悲惨で、恥じて然るべき面も多々あり、今なおその後遺症が近隣諸国の日本観の中に残っているのは残念だ。しかし、「仮想の歴史」なら、日本人の良いところ(誠実で潔いところ)だけを描くことも可能だ。
今なお、現実の日本の過去の歴史を正当化し、少しでも敗戦の屈辱を晴らしたいと考えている人達が多いようだが、私は全く違う考えだ。過去の歴史は冷静に検証し、反省すべき事は真摯に反省し、敗北がもたらした現実は潔く受け入れ、先人達がやってきた事の中に謝罪すべき事があれば、勿論きちんと謝罪する。それは他人からいわれてやる事ではなく、自らの意志でやる事であり、その事に忸怩たる思いを持つ必要は全くない。日本人の良さをどこかで訴えたいのなら、その良さがそのまま実現できたような「仮想の歴史」を考えてみて、その中でそういう「誠実で潔い人物」を描いてみればよいのだ。
実は、「暁の雷鳴」と題するこの大河小説の具体的な「あらすじ」は、私の頭の中では既に出来上がっている。
「革命前夜のロマノフ王朝と李王朝が結束して、日本は韓半島からも追い落とされる。しかし、こうして大陸への足がかりを根底から失ってしまった日本は、結果として植民地主義には遂に一度も手を汚すことがなく、海軍力に頼った専守防衛に徹する一方で、産業の高度化と中南米への移民に活路を求めた。
一方、さしものヒットラーも、日本に備える兵力を東部に配備する必要がないソ連には侵攻出来ず、従ってスターリンとの蜜月が長く維持される。結果として、ポーランドの分割線とイランとイラクの国境線で、ユーラシア大陸は共に独裁的な強権国家である独ソに二分される。
英国は独軍に本土を蹂躙され、豪州に亡命政権を樹てる。日本は英米から懇請されて三国同盟を結び、中国とインドに義勇軍を送って、この両地域への国際共産主義勢力の侵攻を食い止める一方、東南アジアでは英米に植民地主義を放棄させて、民族自立と民主主義をベースとしたアジア共栄圏の建設に注力する」といった筋書きだ。
仮想の歴史のシミュレーションとは言っても、「小説」なのだから、全ての中心は人間だ。「時代の波に翻弄され、漠然たる不安に苛まれる人間の姿」を色々な場面で描いていきたいと思っている。
この物語の主人公は愛国心に燃える日本の陸軍士官だが、若い頃の彼は、共産革命勢力に国を追われて日本に亡命し、その後祖国への反攻を試みて失敗する大韓帝国最後の皇帝(李王朝の最後の国王)の侍従武官に任じられ、過酷な戦場で彼と寝食を共にしつつ、若者同士の心を通わせた。
米英日の三国同盟締結後は、蒋介石を支援する日本の義勇軍の前線の指揮官として、農民の支持を得る事に腐心しつつ、揚子江を挟んで対峙する中共軍と血戦を繰り返した。北方のソ連との間に確執を抱えた毛沢東が、蒋介石と電撃的に和解し、「一国二制度」を基本とする南北中国の連邦国家を樹立した後には、今度は休む暇もなく、彼は「インドへのソ連軍の侵攻に備える多国籍義勇軍の総司令官」に任命される。
そんな絶え間のない戦いの中で、「人間は何故戦わねばならないのか」と彼は常に自問する。そうすると、産業経済の事、植民地主義の事、民族主義の事、宗教の事、イデオロギーの事、そして「不可避的に腐敗する権力」の事、等々に、彼の思いは際限もなく広がっていく。
彼の学友だった経済産業省の若手官僚が、オーストラリア西部に「ニューエルサレム」を建設していた亡命ユダヤ人達の助言を入れつつ、ベトナムとインドネシアで成功させた「民族意識を尊重した自由経済共栄圏」の構想を、今度は英国のお膝元のインドでも実現するのが、今や彼の夢となっていたが、その為には目前の戦争に勝ち抜かねばならない。「そして、その為には多くの人々が死ななければならない」と彼は絶望的な気持で考える。
この物語の最終章で、彼は、少女時代に彼とロンドンで出会って愛しあい、突然の別れを余儀なくされたパキスタン人の女性と、カシミールの前線で邂逅する。迫り来る戦乱を前にして、二人は一夜を共にし、「戦争のない未来」への夢を語り合う。その中で、彼は、独軍の手で虐殺された両親の面影を心に刻みつつ、英国の情報機関の手で「イスラム反共ゲリラとの共闘工作員」に育て上げられていた彼女の心が、何時終わるとも思えない「報復の連鎖」がもたらす将来への不安に、絶望的なまでに苛まれていた事を知る。
「人間は、生きて、死ぬ。それだけのことだ」と、私は常に考えてきた。仕事をしている時、「日本や世界の政治や経済」について考えている時、そして、小説を書いている時には、その折々でそれなりに夢中になってきたし、その事は今も変わらないが、それも私の儚い人生のささやかな一コマに過ぎない。本当の私が何者なのかは、私自身にも最後まで分からないだろう。
私は、自分自身の生死観故に、「樹木葬」による私自身の「墓標のない墓所」を、縁もゆかりもない岩手県の山里に既に確保済みだが、火葬場で焼かれた私の骨の数片がそこに埋められるまでには、まだもう少し時間があるように思う。だから、それまでのしばらくの間は、私は自分自身の自由な意志で、出来るだけ自分の気の済む様に過ごしたい。回りの人達に迷惑をかけさえしなければ、その程度の事は許されるだろう。
具体的には、これまでに嫌というほどやってきた「ビジネス」というものからは完全に自由になって、肩肘を張らず、穏やかな気持ちで、「自分」という「人間」の「純粋な本質」に少しでも近づきたい。「ビジネス」や「事業」というものは、謂わば「止むに止まれぬ戦争」のようなものだから、終わってみれば「空しさ」だけが残るとしても、それはそれでやむを得ない事だ。「人間が作ってきた国や社会を少しでも良いものにしたい」という気持も、この延長線上にあるもので、「ビジネス」や「事業」といったものよりは多少はレベルの高いものであっても、基本的には同じ事だろう。
「悟りの境地」というのはおこがましいが、人間がその不可解な生涯を終える時には、生きてきた日々を彩った全ての葛藤は追憶の彼方に消え去り、生まれてきた時と同様の「ありのままの姿」に戻っているのが、一番良いのではないかと私は思っている。そして、私の場合、その時が来るのはもうそんなに先の事ではない。
2014年7月30日
松本 徹三