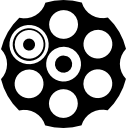「ベンチャービジネス」の挫折 (1986年 - 1988年)
この会社は、私が自分自身で長年構想を暖めていた多機能電話システムを、日本のシャープや大興電機等に作ってもらって、それを米国で販売する為の会社だった。私が開発した商品は、当時七つの地域電話会社(RBOCS)がAT&Tに対抗する戦略商品として売り込もうといていた「セントレックス」のサブシステムとなる筈のものだったから、これなら、彼等の販売組織にも興味を持ってもらえる筈だと踏んでいたのだったが、結果は思うに任せなかった。
「人に頼っていては駄目だ。自分自身で世の中のニーズを先取りして、既存の要素技術を結びつけ、独自の商品を創り出す必要がある。」その様に一人秘かに思い詰めていた私は、「Be creative or die(創造しないのなら、死んだ方がまし)」という標語(米国の独立戦争時代の標語「Be free or die」をもじったもの)を自分で作って、額に入れてCICSの社長室に掲げた。この仕事を始めた当初は、このように気持ちが高揚していたのだが…。
第一号商品として企画した最新鋭の高機能電話機(愛称ESCOM)は、エグゼクティブ同士、或いは秘書とエグゼクティブとの連携機能に重点をおいた「システム志向」の商品だったが、単体としても、これまでにない最高級機と認められることを目標とした。大型のLCDディスプレイと必要な時に引き出せるQWERTYキーボードを具備し、「電話帳」や「ワンタッチコールバック機能」は勿論、「システム内でのメッセージ交換」、「スケジュール管理」、「特定のデータサーベースから必要情報を取り出せる機能」などを内蔵していた。一九八六年の時点だから、世の中に全く存在していなかった機能も多かった。(例えば「グループ内でのメッセージ交換機能」は「E-Mail」と名付けたが、この呼び名を使ったのは世界で初めてだったと思う。)
このシステムの先進性には業界の中でも注目してくれる人が多く、或るコンサルタントの推薦で国防省の高官のオフィスに早々と一システム納入できたし、Dow Jones社は自社の株価表示システムと連動させてくれて、「Dow Phone」というパンフレットまで作ってくれた。しかし、如何せん、このシステムは、売り出してからすぐに致命的な欠陥を露呈した。
私の未熟さ故に、普通の多機能電話機を作る感覚で「機能決め打ち」でソフトを作り込んでしまったのが最大の失策だった。この為、「客からの変更要求に全く応えられない」という問題が早々と露呈した。「売込みにも販売後のトレーニングに手間がかかり過ぎる」「電話システムの拡張性が限られていて、大口の見込み客の要求に応えられない」等々の問題も生じ、あてにしていたRBOCSの販売部門は、「これらの問題が解決するまでは販売には踏み切れない」として「様子見」を決め込み、動いてくれなかった。
そうこうしているうちに、一向に売れない初期ロットは、たちまちのうちに在庫の山になった。折からの急激な円高にも打たれた。
その頃の私には、別途、「伊藤忠アメリカのエレクトロニクス部長」としての広範な職責もあった(その中には、「NTTと一緒にジャマイカでテレマーケティングの会社を創る」という面白いプロジェクトもあった)ので、CICSの社長には早い時期に然るべき米国人を雇う予定だったのだが、こういう状態では誰もこんな会社には来てくれない。仕方がないので自分自身で社長兼務を続行して、毎日の半分以上の時間をこの会社の為に使わざるを得ないという破目になった。
しかし、朝早くから深夜に至るまで働いても、人間が一日に使える時間には限界がある。本社から頼まれる仕事は、「どうしても」という案件以外はついつい他人任せになる。本社から見ると、「あいつは勝手な事ばかりしていて、全く頼りにならない」という事になってしまうのもやむを得なかった。
こうなれば、いくら何でも東京本社での信用は完全に失墜する。先ず「CICSにはこれ以上金は出せない」という限度額を突きつけられた。ということは、「残り少ない時間内に目覚しい業績の好転がない限りは、CICSは倒産するしかない」事を意味する。
「これまでに使ったのと同じぐらいの金を更につぎ込んで、もう一年かけてESCOMを一から作り直し、その間に、別途開発が終わっていた『一般用の安価な電話システム』の方を先行販売することにすれば、RBOCSの販売組織を動かすことは十分可能だ」と考えていた私は、最早何を言っても聞いて貰えそうにない東京本社に頼ることを断念し、これまでに付き合ってきていたベンチャーキャピタリストを口説こうと考えた。
しかし、会社の名前をIBMの向こうを張ってICM(International Communication Machine)とした程の野心的なビジョンや、何日も徹夜して作った詳細な事業計画は、それなりにかなり評価されたが、「それでは何故伊藤忠はこの可能性を放棄しようとしているのか」という問いにはうまく答えられない。そのうちに資金切れの期日はどんどん迫ってくる。情況を察しはじめた従業員達の空気も不穏になる。「倒産寸前の会社」というものはどこでもそういうものなのだろうが、毎日が地獄のようになった。
エレクトロニクス部長を解任された上、「小さなオフィスを一つ用意しますから、当面は既に売ってしまった商品のアフターサービスだけを、一人でやっていてください」と、本社のかつての自分の部下に求められたこの時期が、私にとっては文字通り「人生のドン底」だった。「成程、自分一人なら夜逃げも出来ようが、伊藤忠の名前で売ってしまった商品ならアフターサービスをしないわけにはいかない。会社がお前一人でやれというのなら逃げられないというわけか!」そう考えると、流石に目の前が真っ暗になった。
しかし、誰を恨むわけにも行かない。全て自分で決めて自分でやったことだ。この頃になると、このような事態を招くに至った自分の多くの「判断の誤り」が、自分自身でもよく分かるようになっていたので、拭っても、拭っても、頭から離れない悔悟の念に、身を切られるような毎日が続いた。(この辺の話は、後述する久慈毅著「新規事業室長を命ず」で少しだけ触れられている。)
それからの必死の努力のおかげで、辛うじて「従業員の全員引き取り」と「アフターサービス」を西海岸にあった或る新興企業に引き受けて貰えたので、私自身は虎口を脱することが出来たが、その後この会社がこの商品ラインを生かして成長したという話は聞いたことがなかったから、結局は大きな迷惑をかけたのだろう。その事を思うと、今でもとても辛い。
会社売却の交渉を通じて、相手方に対して真実を糊塗した事は一切ないと断言出来るが、「夢を語り過ぎなかったか?」「気掛かりな事を全て洩れなく話したか?」と問われれば、胸は張れない。如何に「自分が生き残る為」だったとは言え、この事については、今に至るも、私の心の中で罪の意識が消える事はない。