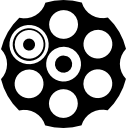屈辱に耐えての帰国 (1988年)
その後、本社からは「すぐに日本に帰って来い」という指示があったが、その気にはなれず、一人で秘かに米国での新しい職場探しを始めた。「あんたは日本に帰れば仕事があるのだからいいよな」と嫌味を言ってきたCICSの米国人の部下達に、「何を言うか。勿論私も伊藤忠を辞める」と大見得を切っていた手前もあり、自分だけのこのこ日本に帰るわけには行かないと思っていた。
つまらない「男のプライド」から、「伊藤忠時代より地位や給料が下がるのは嫌だ」という気持が先行し、この為に仕事探しは難航したが、そのうちに、これまでの仕事を評価してくれていた或る米国人の斡旋で、ノースキャロライナにあるノーザンテレコム社の交換機事業部のVPに採用して貰うことがやっと決まった。
正式な採用通知を貰った時には心底からホッとしたが、ホッとして伊藤忠に辞表を提出したその直後に、国際事業を巡っての同社の複雑な内部事情(カナダ本社と事業部との綱引き)が判明、同社に入っても難しい立場に立たされる心配が出てきた。自分の本領は何といっても「日本をよく知っている」という事だ。それなのに、内部抗争に巻き込まれ、その得意分野を生かせられなければ、よい成果は出せるわけがない。米国の会社だから、成果が出せなければやがて放り出される。私は頭を抱えた。
「この状況下で自分はどうすればよいのか?」しばらくの間、この事について相当思い悩んだが、ここでまた一から職探しをするとなると、家族の生活を守っていける自信が持てない。そうなると、やはり日本に帰るしかない。遂に、意を決して、ノーザンテレコム社への入社も、更なる職探しも諦め、恥を偲んで伊藤忠の本社に電話をした。「あのう、辞表を出してしまっているのですが、もしかして、今からでも撤回させてもらうことは出来るのでしょうか」と恐る恐る聞くと、「ああ、いいよ。やってもらいたい仕事は山ほどあるから、帰ってきなさいよ」という返事が返ってきた。
こんな屈辱的なことはなかったが、家族のことを考えるとやむを得なかった。何よりも三人の子供達の教育を犠牲にするわけにはいかないと思った。こうして、私は、書類を整えて伊藤忠への復帰を認めて貰い、帰国の日取りも決まった。
しかし、どんな会社のどんな組織でもそうだろうが、「相当額の損失(今から考えると、さして大きな額ではなかったが)を出した上に、既に辞表を受理して退社が決まっている社員には、最低の評価点をつけて、他の社員への得点の配分を少しでも良くする」のが組織の管理者の常識だ。復帰が決まった時には、既にこの評価は人事部に登録済みだったので、採点者としても今更書き換えるわけには行かない。こうして、私の東京本社への帰任は、「CCC」という史上稀な「最低評価」の烙印を背負っての帰任となった。伊藤忠の内規では、こういう評価が一旦付いてしまうと三年間は消えない。