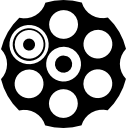結局避けられなかった伊藤忠との離別 (1996年)
しかし、この間に、タイムワーナーとの関係を始めとして、周辺では色々なことが起こり、衛星事業に関係しての4商社間での綱引きも始まっていたので、様々な思惑が交錯する社内外の駆け引きに、私は嫌気がさすことが多くなっていた。
その頃には、私は通信事業部長から新設のマルチメディア事業部長に横滑りし、その後、「情報産業」「通信・メディア」「航空機・防衛産業」を統括する「宇宙情報部門」の部門長代行に就任していたが、この部門の部門長(取締役)には、結局入社年次で一年後輩になる「稼ぎ頭の情報産業本部」の出身者が選ばれた。当然といえば当然の事だったが、こういう流れになると、これ以上伊藤忠にいても昇進のチャンスはあまりないのも事実だ。
いや、仮に昇進のチャンスがあったとしても、そこで自分の思う方向に会社を持っていけるという自信は、私には全くなかった。少なくとも情報通信産業の分野では、主力は全て「総合商社」の枠の外に出てそれぞれの道を歩み、本体は最小限の人員で「投資」のみを行うべきだと私は考えていたが、その様な過激な考えが上層部に容れられる可能性は、当時は殆どなかった。
後に急逝する私の当時の直接の上司の森亮人さんは、次期社長が確実視されていた人で、私は彼から「政治的な動き方」等については実に多くのことを学んだが、経営についての考え方は相当違っていた。
(ちなみに、私の退社後、急逝した森さんに代わる社長候補に急浮上した丹羽宇一郎さんの方が、「経営理念においては自分と近い」と私は思っていた。丹羽さんは私と同期入社で、私とは仲もよかった。既に退職していた私を、彼は或る日夕食に招いてくれて、「ここまで来たら、自分が腹を決めて社長になり、積年の膿を全て出す」という決意を、わざわざ披露してくれた程だった。丹羽さんはその後伊藤忠の経営を軌道に乗せて「大物財界人」として名を売り、後に中国大使になった。)
何れにせよ、この様な状況下では、結論は目に見えていた。私は、常日頃から、後輩の配慮で関係会社の役員に「天下る」様なことだけは絶対にしたくないと思っていたので、「そろそろ伊藤忠を辞める汐時かな」と考えるに至ったのも当然だった。思えば、48歳で失意に打ち拉がれて米国から帰国し、「伊藤忠に在籍するのはしばらくの間」と考えていた時から、知らぬ間に7年以上が経っていたのだ。
「伊藤忠から離れたいと」いう気持を持った背景には、実は「NTT問題」もあった。伊藤忠の基本的な戦略は、「衛星通信や国際通信事業で世話になっていたNTTとの緊密な関係を堅持し、その力を利用して日本の情報通信産業界での地歩を固めていく」ということであり、それは伊藤忠のおかれた立場からすれば極めて理にかなったものではあったが、私の目から見れば、主体性のない「小判鮫商法」のようにも見えた。何れにせよ、「通信の自由化を梃子に新興勢力をつくり、既存勢力に対抗したい」という自分の「心情」とは、基本的に相容れないものだった。
ちょうどその頃、経団連では、各社の部長級で構成される「情報通信産業の将来像を考える」タスクフォースが、NTT分割問題についての意見具申を求められていた。私はその構成メンバーに選ばれていたので、そこでは「会社の立場」と「自分自身の信条(心情)」との相克に深く悩むことになった。「NTTの組織防衛」に組みすることは、伊藤忠の立場としては当然の義務だったから、私も実際にそうしたが、自分の一生を委ねる選択としては気が進まず、内心は鬱々としていた。
この事には別の側面もあった。副会長を最後に伊藤忠から離れた瀬島龍三さんは、伊藤忠の中でもなお隠然たる影響力を持っていたが、彼はNTTの取締役にもなっており、伊藤忠とNTTを結びつけることに熱心だった。従って、伊藤忠の中にとどまる限りは、事の如何を問わず、NTTと事を構えることなどは不可能と言ってもよいと思われた。
しかし、大袈裟に言えば、「こんなことをしていては、日本の情報通信産業は米国などに比べて大きく後れを取る」というのが、その当時からの私の強い考えであり、その後のどんな時でもその考えが変わることはなかった。NTTには親しい人が沢山いたし、そういう人達は全て素晴らしい人達ばかりだったが、「組織になると、何故か極端に閉鎖的で保守的になる」と私は思っていた。
色々なことが重なり、次第に決意が固まっていった。「そのまま伊藤忠グループの中にとどまるという選択肢は、どう考えてみてもない」と思うに至る一方で、「人生は一度しかない。もう一度ベンチャーで勝負して、自分の基本的な考えが正しかったことを証明してみたい」という高揚した気持もあった。
その頃には、日本でもベンチャービジネスというものに対する理解は高まりつつあったし、今度は初めから「通信」にこだわらず、また「ハードウェア」にもこだわらず、ネット上で動くユニークなアプリケーションの世界で勝負すれば、勝算は十分あると考えた。明確なアイデアがあったわけではないが、ビジネスマンを対象とする「ソシアル・ネットワーク」のようなものの構築を、漠然と考えていた。もし実現していたら、ずっと後になって出てくる米国のLinkedInに近いものに発展していたかもしれない。