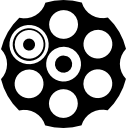ニューヨーク駐在時に通信機ビジネスを開拓 (1974 - 1982年)
2年間の東京勤務が終わると、約束通り、たまたま空いたポジションがあった「シカゴ駐在員」にして貰った。しかし、「食品、医療、包装などの分野で米国から輸入出来る新しい機械類を、何でもよいから探せ」というこのポジションは、既に時代遅れだったし、独立採算で運営するには無理があり、1年でニューヨークに転勤になった。
ニューヨークでも採算に乗るビジネスはなかなか見つからなかった。自分で稼げないと、セクレタリーさえ満足に使わせてもらえない。
ユダヤ系の米国企業が作るダンボール製造機器を、アルジェリア向けに石川島播磨が売り込んでいた製紙プラントの中にもぐりこませるとか、皇帝が強大な力を持っていた当時のイランが、イラクと束の間の関係改善を計った時に、イランの港に滞在するイラクの税官吏宿舎用にアメリカ製のモバイルホーム(家具調度品付きの簡易ホーム)を輸出するとか、当時脚光を浴びつつあった「国交回復前の米中貿易」の仲立ちをするとか、色々なことを試みたが、何をやってみても、そう簡単には結果は出ない。
「どうして食い扶持を稼いだものか」と思いあぐねていたところ、たまたま以前に一緒に仕事をした先輩が東京本社の「通信プラント部」の課長をしているのに気がついて、この人に「貴部だけがアメリカと全く関係を持っていません。私に年間1万ドル払ってくれたら何でもやりますから、考えてみてくれませんか」という手紙を書いた。この人は最後まで1万ドルは払ってくれなかったが、その代わり日本製の電話機などのカタログの束を送ってきた。
見るからにダサいカタログの束を見て、「こんなものがアメリカで売れるわけはないじゃあないか」と腹を立て、まとめてゴミ箱に放り込もうとした時に、ちょっと変わった形の電話機の写真と英文でタイプされた二枚の紙が目に留まった。これが、松下通信工業(現在のパナソニック・モバイルコミュニケーション)が世界に先駆けて開発したマイクロプロセッサー制御のボタン電話システムだった。松下はこれを電電公社にもっていったが全く相手にされず、「それでは輸出するしかない」ということで、藁にもすがる思いで各商社に持ち込んでいたらしかった。
それから色々な苦労があったが、結局、ここから始まった「ビジネス用電話システム」の対米輸出が、結構大規模なビジネスになる見込みがついたので、本社の「通信プラント部」の中に課を一つ新設してもらって、そこの課長として帰国することが出来た。私歳の時のことで、それ以来、私の「通信」との30年近くに及ぶ関係が始まる。
しかし、それからの約五年間は苦労の連続だった。順調に拡大していた松下のビジネスも、大型PABXシステムを手掛けだしてから技術の壁に阻まれ、トラブルが続発した。課員にまともに英語の出来る人間がいなかった為、課長の私自身が夕刻の五時頃から横浜の松下の工場に出向き、技術者の作るトラブル対策の手順などを翻訳して米国の販売業者に送り、最後の一人になるまで仕事をして深夜に帰宅するような生活を続けた。
現地に飛べば飛んだで、客先のセクレタリーに頼み込んで、「電話が途中で切れる。こんなことでは仕事にならん」と怒り狂う個々のユーザーからログを取ってもらったり、終業後のオフィスで深夜まで回線の繋ぎ変えをしたりと、泣きたくなる様な仕事ばかりが多かった。にもかかわらず、松下側からすれば、「そろそろ伊藤忠に手数料を払い続けるのは止めたい」と思うのは当然で、色々な局面で仕事から外される危機があり、私は「仲介業者」の悲哀を噛み締めさせられた。
課長として課員を路頭に迷わせるわけには行かなかったから、私は多くの屈辱に耐えたが、自分自身の心の中では、「仲介業なんかは早くやめて、メーカーで仕事をしたい」という欲求が抑え難くなっていた。長い間ずっと松下通信工業の技術開発チームの中で一緒に仕事をしていたので、門前の小僧も経を読み、特に新しい機種を創り出す事に対する興味が、人一倍強くなっていた。
この為に、後に某メーカーから責任のあるポジションを提示されて誘われた時には、真剣に転職を考えた事もある。