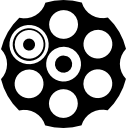(付記) 死ぬまでにやりたいこと
今や世界的な事業家の一人である孫さんとは異なり、ビジネスの世界では、私は所詮は小さな存在にしかなれなかった。
何にでも好奇心を持ち、色々なことをやってきた割には、まだ生き延びているのだから、運が良い方であったことは間違いないと思うが、残念ながら、自分自身の潜在的能力は、生涯を通じて結局は半分も生かせなかったように思う。しかし、それは、自分にガッツがなかったからだし、それにもう済んでしまった事だ。孫さんの「30年構想」のようなものを、私は元々全く持ち合わせていない。つまり、私は本当の意味での事業家ではなかったのだ。
しかし、その一方で、「人の一生というものは、もっと幅の広いものであるべきだ」という強い思いが私にはある。運よく80歳を越えるまで、頭もあまり呆けることなく生きられるとすれば、今手掛けている仕事は77歳を堺にして徐々に減らして、その後は、全く別の事に、自分自身の時間をもっと割きたいと思っている。
日本の将来への貢献という面では、「教育現場の改革」の為に役立つ事を何かやりたい。私は、常日頃から「今の大学教育のあり方はおかしい」とも思っている。特に興味があるのは、「国内外の若い人達に幅広い知識の吸収と交流の場を提供する事」だ。情報通信技術の活用がその為には欠かせない。こういう事は、既に先人達が多くのことを手掛けているが、自分もその中に飛び込んで何等らかの手助けをしたい。
そういった事も意識しながら、自分でも一つか二つ大学や大学院で講座を持ってみたいと考えていたところ、幸いにもご縁があって、明治大学専門職大学院のグローバルビジネス研究科長の木村哲先生からお声がけを頂き、20年の秋から同大学院の「特別招聘教授」を勤めさせて頂いている。自分で言うのも変だが、かなり情熱的な授業が出来ていると思うし、私自身の実体験に基づいた授業は、それなりに受講生の興味も惹いているだろうと思っている。この立場を手掛かりに教育問題にもっと深く関与出来れば、望外の幸せだ。
しかし、それ以上にやりたい事が私にはある。「やりたい」というよりは、「やらなければならない」事だと言ってもよいだろう。それは、自分の周りに謎めいて存在する「世界」と、不可避的にそれと関わっている「自分自身」を見詰め直す事だ。そして、それに近いところにあるものとして、私には「文学」がある。
私は、今から10年以上前に、「久慈毅」というペンネームで、読み物仕立てのビジネス書を3冊、ダイヤモンド社から出版して貰ったことがあるが、その後は「純文学」を志して、「外村直樹」という新しいペンネームで、既に、長編を2編、中編を8編書き下ろしている。「感性が衰えないうちに書き上げてしまわなければ」という思いで、長い年月をかけて、夜や週末に精力的に書き続けてきたものだが、中編1編をある文学雑誌に掲載してもらった以外は、全て未発表だ。
「外村直樹」の作品群の内容は、自分としては全て極めて哲学的なものであると思っているが、筆者の年齢から想像されるような「枯れたもの」ではない。それでも、その殆どが、ビジネスの世界での私からは想像し難いような「諦観」と「不条理」がテーマになっている。ちなみに、人はよく「不条理」という言葉に特別な思いを込めて使うが、私は「この世界は元々『不条理』でしかあり得ず、『条理』が全ての根底にあると信じなければ生きていけないような弱い人間に、私はなりたくはない」と、密かに心に決めている。その事自体が、私が生きてきた事の証だと思っているからだ。こういう本を普通に出版してもらうのは難しいが、電子書籍が一般化してハードルが下がれば、一括して世に問いたい。
その意味からも、電子出版の市場拡大にも大きな関心を持っている。今は時代の転換期、全てが「双方向」の世界へと大きく動いている。これからは、同じような考えや感性を持つ老若男女の人達が、それぞれにネット上で自由に交流出来るようになるだろう。文学の世界も、一握りの出版社の商業主義のくびきから自由になり、昔の同人雑誌のようなみずみずしさを取り戻せるかもしれない。
あまりに気が多いので呆れられるかもしれないが、私は「歴史」の勉強にも強い興味を持っている。新しい技術は次々に出てくるのでもう追いきれないが、歴史の勉強なら過去の事を追うだけでよいので、そのようなプレッシャーはない。
特に、明治維新以降の日本とその周辺国の歴史は、もっと勉強したいと思っている。そして、その勉強の結果をベースとして、「日露戦争から太平洋戦争までの時代」を背景に、「仮想的な歴史大河小説」を書きたいと思っている。「日本がもし日露戦争に勝てていなかったら、世界の歴史は全く違ったものになっており、その中で日本はこんな国になっていたかもしれない」というのがテーマだ。
実際の歴史は悲惨で、恥じて然るべき面も多々あり、今なおその後遺症が近隣諸国の日本観の中に残っているのは残念だ。しかし、「仮想の歴史」なら、日本人の良いところ(潔いところ)だけを描くことも可能だ。今なお、現実の日本の過去の歴史を正当化し、少しでも長年の屈辱を晴らしたいと考えている人達が多いようだが、私は全く違う考えだ。過去の歴史を反省し、敗北がもたらした現実は潔く受け入れ、謝罪すべき事があればきちんと謝罪する。その事に忸怩たる思いを持つ必要はない。日本人の良さをどこかで訴えたいのなら、その良さがそのまま実現できたような「仮想の歴史」を考えてみて、その中でそういう潔い人物を描いてみればよいのだ。
実は、「暁の雷鳴」と題するこの大河小説の具体的な「あらすじ」は、私の頭の中では既に出来上がっている。「革命前夜のロマノフ王朝と李王朝が結束して、日本は韓半島からも追い落とされる。しかし、こうして大陸への足がかりを根底から失ってしまった日本は、結果として植民地主義には遂に一度も手を汚すことがなく、海軍力に頼った専守防衛に徹する一方で、産業の高度化と中南米への移民に活路を求めた。一方、さしものヒットラーも、日本に備える兵力を東部に配備する必要がないソ連には侵攻出来ず、スターリンとの蜜月が長く維持される。結果として、ポーランドの分割線とイランとイラクの国境線で、ユーラシア大陸は独ソに二分される。英国は独軍に本土を蹂躙され、豪州に亡命政権を樹てる。日本は英米から懇請されて三国同盟を結び、中国とインドに義勇軍を送って、この両地域への国際共産主義勢力の侵攻を食い止める一方、英米に植民地主義を放棄させて、民族自立と民主主義をベースとしたアジア共栄圏の建設に注力する」といった筋書きだ。
(仮想の歴史のシュミレーションとは言っても、「小説」なのだから、全ての中心は人間だ。「時代の波に翻弄され、漠然たる不安に苛まれる人間の姿」を色々な場面で描いていきたいと思っている。この物語の主人公は愛国心に燃える日本の陸軍士官だが、若い頃の彼は、共産革命勢力に国を追われて日本に亡命し、その後祖国への反攻を試みた大韓帝国最後の皇帝の侍従武官として、若い皇帝と寝食を共にしつつ心を通わせた。米英日の三国同盟締結後は、蒋介石を支援する日本の義勇軍の前線の指揮官として、農民の支持を得る事に腐心しつつ、揚子江を挟んで対峙する中共軍と血戦を繰り返した。毛沢東と蒋介石の和解と南北中国の連邦化の後には、今度は休む暇もなく、インドへのソ連軍の侵攻に備える多国籍義勇軍の総司令官に任命される。そんな絶え間のない戦いの中で、「人間は何故戦わねばならないのか」と彼は常に自問する。最終章では、彼は、少女時代に彼とロンドンで出会って愛しあい、独軍の手で虐殺された両親の面影を心に刻みつつ、英国の情報機関と亡命ユダヤ人組織の手で「汎イスラム反共ゲリラ」との共闘工作員に育て上げられていたパキスタン人の女性と、カシミールの前線で邂逅し、戦争のない将来への夢を語り合う。)
「人間は、生きて、死ぬ。それだけのことだ」と、私は常に考えてきた。仕事をしている時は、その折々でそれなりに夢中になってきたが、それも私の儚い人生のささやかな一コマに過ぎない。本当の私が何者なのかは、私自身にも最後までわからないだろう。
私は、「樹木葬」による私自身の「墓標のない墓所」を、縁もゆかりもない岩手県の山里に既に確保済みだが、そこに埋められるまでには未だ少し時間がある。だから、それまでのしばらくの間は、これまでに嫌というほどやってきた「ビジネス」というものからは完全に自由になって、純粋な気持で、「人間」というものを、そして、その「人間」が作る「国」や「社会」の事を考えながら、色々な事をして過ごしていきたいと思っている。
2014年6月30日
松本 徹三